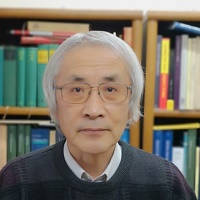学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
名古屋大学文学部 人文学科 文芸言語学コース フランス語フランス文学分野HPへ【フランス文学(特に「生成研究」)】 小説等の原稿の調査から作品の誕生のプロセスを探究するのが「生成研究」であるが、その分野の複数の専門家が教鞭を取っており、「生成研究」の方法を身に付けるには最適の学部・研究室である。 |
神戸大学国際人間科学部 グローバル文化学科HPへグローバルイシューについて学ぶ「グローバル・スタディーズ・プログラム」に学部生全員が参加することになっており、特に海外フィールド学修が充実している。 |
愛媛大学法文学部 人文社会学科 グローバル・スタディーズ履修コースHPへ【多文化地域の文学・文化研究】 |
鹿児島大学法文学部 人文学科 多元地域文化コースHPへ【多文化地域の文学・文化研究】 |
学習院大学文学部 ドイツ語圏文化学科HPへ【ドイツ語学】 ドイツ文学のみならずドイツ語学関係のスタッフが充実している。ドイツ語ネイティブの教員がいわゆるドイツ語教師ではなく、文学・文化学の専門家であることもポイントが高い。 |
慶應義塾大学文学部 人文社会学科 独文学専攻HPへ【ドイツ文学】 中世神秘思想から現代のメディア論まで、幅広いテーマをカバーできるスタッフが揃っている。教員一人一人のレベルも高く、優秀な若手研究者を育てている。 |
国際基督教大学教養学部 アーツ・サイエンス学科 文学メジャーHPへ【多文化地域の文学・文化研究】 |
早稲田大学文学部 文学科 フランス語フランス文学コースHPへひと口に「フランス文学」といっても実態は多様であり、そのなかにはフランス語で書かれた植民地出身の文学も含む。早稲田にはフランスに関わる多様な専門家がいるのが魅力である。 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
竹内修一 先生
北海道大学 文学部 人文科学科 言語・文学コース/文学院 人文学専攻 【アルベール・カミュ研究】アルベール・カミュの哲学的側面、特にエッセイ「反抗的人間」に表明された反全体主義的思想に関して、世界的なレベルの論文を発表している。 HPへ |
 |
柳原孝敦 先生
東京大学 文学部 人文学科 現代文芸論専修課程/人文社会系研究科 欧米系文化研究専攻 【ラテンアメリカ文学】研究の中心はアルフォンソ・レイェス(メキシコ)と、アレホ・カルペンティエール(キューバ)。20世紀のラテンアメリカ文学に大きな影響を与えたラテンアメリカの作家を研究する。『チェ・ゲバラ革命日記』の翻訳もしている。 HPへ |
 |
鈴木正美 先生
新潟大学 人文学部 人文学科 言語文化学主専攻プログラム/現代社会文化研究科 社会文化専攻 【ロシア文学】ポーランド出身のロシアのユダヤ系詩人マンデリシュタームをライフワークに、現代ロシアの詩を研究している。 HPへ |
 |
番場俊 先生
新潟大学 現代社会文化研究科 現代文化専攻 【ロシア文学】ドストエフスキーなどロシア近代小説論を展開。一方「顔」や「声」をキーワードとする表象文化史の二つを軸に研究を進めている。 HPへ |
 |
安川晴基 先生
名古屋大学 文学部 人文学科 文芸言語学コース ドイツ語ドイツ文学分野/人文学研究科 人文学専攻 【想起文化】ナチズムなど歴史と向き合う現代ドイツの想起の文化を広い視野から考察している。 HPへ |
 |
岩本和久 先生
札幌大学 地域共創学群 人間社会学域 リベラルアーツ専攻 【ロシア文学】ロシア・スラヴ地域を研究し、主著に『フロイトとドストエフスキイ 精神分析とロシア文化』あり、優れた研究能力に定評。 HPへ |
 |
川島建太郎 先生
慶應義塾大学 文学部 人文社会学科 独文学専攻/文学研究科 独文学専攻 【メディア論】「記憶/想起」をキーワードに自伝と写真との関係を論じた論文が秀逸。 HPへ |
 |
宮崎麻子 先生
立教大学 文学部 文学科 ドイツ文学専修/文学研究科 ドイツ文学専攻 【現代文学と記憶、ドイツ文学】ポスト東ドイツ文学に加え、ナチ期以降の亡命文学における記憶というテーマや、記憶概念の変容についても考察するなど、現代ドイツ文学をよく読み込んでいる。 HPへ |
 |
鈴木雅雄 先生
早稲田大学 文学部 文学科 フランス語フランス文学コース/文学研究科 【フランス文学】1920年代のフランスで始まった文学運動のシュルレアリスムを研究する。サルバドール・ダリのようなシュルレアリスム画家も。 HPへ |
 |
松永美穂 先生
早稲田大学 文化構想学部 文化構想学科 文芸・ジャーナリズム論系/文学研究科 人文科学専攻 【現代ドイツ文学・翻訳論】翻訳家として有名で、現代ドイツ文学を数多く日本に紹介している。ドイツで執筆活動を続け、ドイツ語でも20冊以上出版する作家、多和田葉子の優れた読み手でもある。 HPへ |
 |
寺尾隆吉 先生
早稲田大学 社会科学部 社会科学科/先端社会科学研究所 【ラテンアメリカ文学】政治・社会問題の暴力的な小説をテーマにしたラテンアメリカ文学を研究してきた。最近、映画、音楽、サッカーなどがどのように人々に受け入れられていくのか、ポピュラーカルチャーの社会的影響を考察している。 HPへ |
 |
玉田敦子 先生
中部大学 人文学部 共通科目/中部高等学術研究所 【フランス文学】18世紀フランス文学・思想、近代ヨーロッパにおける教養教育について研究する。 HPへ |
 |
加藤有子 先生
名古屋外国語大学 世界教養学部 世界教養学科 【ポーランド文学】ポーランドの文学、美術、公共空間におけるホロコーストの記憶のジャンル横断的な研究をする。 HPへ |
おすすめ本
かもめ
チェーホフ
『かもめ』は、アントン・チェーホフが1895年に書いた戯曲です。『かもめ』をはじめとするチェーホフの戯曲は、時をおいて読み返すごとに、登場人物の感情や性格について新しい発見をもたらしてくれます。若い時に読むのと、中年、老年になってから読むのでは、作品がまったく違った顔を見せると思いますので、ぜひ最初は若い時に読んでみてください。
日本語にも何度も翻訳されていますので、書店で最初のページを読み比べて自分の好きな翻訳を探すのも興味深いと思いますが、若い皆さんには沼野充義氏の新しい翻訳が読みやすいのではないかと思います。翻訳とは、本来この名訳のように長年の研究と経験の賜物であり、優れた翻訳は、魅力溢れる未知の世界への扉を開いてくれます。
(訳:沼野充義/集英社文庫)
世紀末芸術
高階秀爾
フランス19世紀末は、作家と画家の交流が盛んでした。本書の初版の刊行は今から60年以上前ですが、入門書としての価値を失っていません。印象派への反動から生まれた世紀末芸術は、フランス国内で自然に発生したのではなく、世界との同時代的なつながりを持った運動でした。
本書ではイギリスやベルギーなどとの関係も扱われています。また、皆さんもよく知るゴッホは、フランスで活躍しましたが、オランダ人です。文化に国境はないとよく言われますが、世紀末の芸術家たちは、現代に通じるようなグローバルな感性を備えていたのです。ぜひこの点に注目して、本書を読んでもらえればと思います。時代に先駆けた名著です。
(ちくま学芸文庫)
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。