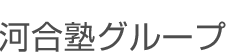私が研究しているフランスのノーベル賞作家アルベール・カミュは、『手帖』と呼ばれる「日記」兼「創作ノート」を亡くなる直前まで使用していました。『手帖』は、カミュが1960年に交通事故で亡くなった後、遺族や友人たちによって出版されました。しかし、『手帖』は単なる「日記」以上の意味を持っています。それは、『手帖』がカミュ自身によって修正を加えられたものだったからです。私は、『手帖』にあとから加えられた修正の内容と、最初に書かれた原稿とを精査して、作家の「真実」に迫ることを研究の目的としています。
「言葉で表現された私」と「本当の私」を探る

カミュの『手帖』の原稿に加えられた修正の内容から見えてくるのは、「『言葉で表現された私』と『本当の私』のあいだにある距離」という問題です。カミュが、自分の「日記」兼「創作ノート」にあとから修正を加えたのは、「自分の過去を偽るため」ではなく、加筆や表現の工夫によって「自分の『真実』に近づくため」だったと思われます。しかも、カミュは『手帖』の修正だけでは満足せず、「真実」にさらに近づくために、ジャック・コルムリーという名の男を主人公とする小説の創造(遺作『最初の人間』の執筆)に向かいます。
実は、小説と比べたとき、日記こそが「真実」だとは言い切れません。あとからふりかえってわかる「真実」もあれば、小説にすることによってやっと近づける「真実」もあるからです。
カミュにとっての「真実」を探るため、フランスの図書館に所蔵されている『手帖』の原稿を精査し、修正・推敲のプロセスをたどっています。作家の執筆スタイルが手書きからパソコンへと完全に変わってしまったり、現存する資料の劣化が進んだりすれば、このような原稿の分析はできなくなってしまうため、こうした研究はいわば「期間限定の急務」なのです。

ゼミ生と学部図書館にて(「日・EUフレンドシップウイーク」 のアルベール・カミュの展示の前で)
一般的な傾向は?
- ●主な業種は→運輸、旅行、金融
- ●主な職種は→事務、営業
分野はどう活かされる?
国際関係学部の学生を対象に、ふだんのゼミでは、フランスやヨーロッパの歴史や文化に関する研究の指導をしていますが、特にゼミの3年生には、カミュの『異邦人』や『ペスト』を読み、「言葉による真実の探求」という問題をじっくり考えてもらう機会を設けています。その後、4年生になると、一人一人が自分なりの問題を設定し、それぞれの「真実」を解明すべく、卒論の執筆に取り組みます。半年あるいは1年間の留学をするゼミ生も少なくなく、運輸(JRや航空会社の客室乗務員など)や旅行・ホテルといった業界に就職するケースが目立ちます。
カミュは、その生涯を通じて、言葉によって「真実」を探究しようとした作家です。そして、言語による「真実」の探究は、大学を問わず、文系の様々な学部・学科で行われている研究の共通の特徴と言えるでしょう。
フランスの植民地だったアルジェリアの貧しい家庭に育ち、文字が読めない家族に囲まれて成長したカミュは、奨学金を得て進学し、ジャーナリストとして活躍したあと、作家になり、ノーベル文学賞を授与されます。
まさに、言葉を自らの力とすることによって栄光を得た人生と言えそうですが、作家カミュの根底にあるのは「言語への不信」です。明解な文体の作品を書き続けた彼には、「我々がこの上なく誠実であるときにこそ、言葉が我々を裏切ることが多い」という思いがありました。他者も自分も裏切らぬよう、言語の使用に可能なかぎり慎重であろうと努めながら、社会と人間と自分の「真実」に、言葉によって迫ろうとすること。カミュが作品を通じて我々に伝えているこのことを、ぜひ、大学という場で皆さんに実践してほしいと思います。
法学部や経済学部などと異なり、国際関係学部では、まず、様々な分野の学問を、広く浅く学んでいきます。もちろん、「国際関係学」という専門分野も1年次から学び始めますが、ひとつの学問では解決できない問題に、学問領域を越え、個々の国や地域の境界を越える視点からアプローチするためには、広い視野を持って学習することが必要なのです。一方、4年次における卒業論文の執筆のためには、ピンポイントの問題を、狭く深く探究することが必要になります。
以上のことから言えるのは、国際関係学部は、国際的な問題に興味を持ちながらも、どの学部に進むべきなのかを決めかねている高校生に、特に推奨したい学部だということです。1~2年次のあいだに、「○○学」というひとつの分野にとらわれず、複数の学問領域の知識を身につけながら、3~4年次に何を自分の研究対象にすべきなのかを、時間をかけて絞り込んでいくことのできる学部なのです。

授業にて

興味がわいたら~先生おすすめ本
アンネの日記 増補新訂版
アンネ・フランク
『アンネの日記』が最初に出版されたのは1947年。アンネが強制収容所で亡くなってから約2年後である。元々の日記に、2度修正が加えられている。1度目は、アンネ自身が将来の出版を想定して加えた推敲。2度目は、アンネの死後、父親のオットーが日記の出版に際して行った修正。文春文庫の「増補新訂版」では、この推敲・修正と、オットーが1980年に死去した後に世に出た2種類の『アンネの日記』(「研究版」と「完成版」)に関する経緯が解説されている。その解説を読み、二人が加えた推敲と修正に思いを馳せながら本書を読んでほしい。「出版」を期して清書されていたこの『日記』は、「日記」であると同時に、未来の「読者」を想定して書かれた優れた「文学作品」とも言えるものなのである。 (深町眞理子:訳/文春文庫)
ペスト
アルベール・カミュ
2020年、コロナウイルスの感染拡大とともに、日本を含め世界中でベストセラーになったカミュの小説。主人公の医師リウーが献身的に病気と闘う物語は、リウーが「彼」という代名詞で語られているものの、読者にとっては、まるで彼の「日記」を読んでいるかような臨場感にあふれており、「日記から小説へ」という観点から読んでも興味深い作品である。
「194x年」に、フランスの植民地アルジェリアのオランという町で突然発生したペストは、封鎖された町の中で猛烈な勢いで広まり、住民を孤独と恐怖におとしいれる。2020年にこの作品が読まれたのは、ペストとコロナウイルスのあいだの「感染症」という共通点によるものだが、『ペスト』は感染症のみに関する小説ではない。元々カミュはペストを人間に襲いかかる「悪」の象徴と考えていた。1947年の出版直後、ペストと戦うオラン市民にフランスの読者が重ね見たのは、ナチス・ドイツによる占領下で闘った「レジスタンス」の活動家たちの姿だった。そして、2011年、東日本大震災と未曾有の原発事故に日本が襲われたときにも、多くの人々が「生きる指針」を求めて『ペスト』を手に取った。
危機的な状況に襲われるたびに『ペスト』が読まれる理由は、この小説にちりばめられた、次のようなカミュの言葉によるのだろう。「絶望に慣れることは、絶望そのものより、もっと悪い。」「人間には、軽蔑すべきものよりも、感嘆すべきものの方がたくさんある。」
(宮崎嶺雄:訳/新潮文庫)