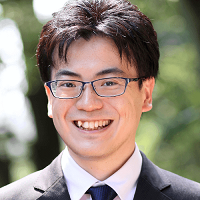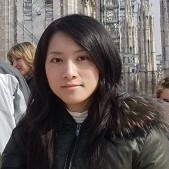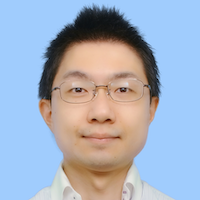学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
金沢大学理工学域 生命理工学類HPへ【生命科学全般】 生命情報分野の研究室あり。 |
岐阜大学工学部 電気電子・情報工学科 情報コースHPへ【バイオインフォマティクス】 バイオインフォマティクスを含む情報科学のテーマを幅広く網羅。 |
九州工業大学情報工学部 生命化学情報工学科 医用生命工学コースHPへ生物と情報の両方を学び、新しい学問分野を開拓している国立大学で唯一の学科である。 |
慶應義塾大学理工学部 生命情報学科/環境情報学部 環境情報学科HPへ【生物学、バイオインフォマティクス】 |
早稲田大学基幹理工学部 情報理工学科/先進理工学部 電気・情報生命工学科HPへバイオインフォマティクス、セキュリティを含む情報科学のテーマを幅広く網羅 |
関西学院大学生命環境学部 生命医科学科HPへ【生物学、バイオインフォマティクス】 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
岡田眞里子 先生
大阪大学 理学部 生物科学科/理学研究科 生物科学専攻 【システム生物学】哺乳類のがん細胞の生化学ネットワークの動力学モデルの第一人者である。 HPへ |
 |
菊地武司 先生
立命館大学 生命科学部 生命情報学科/生命科学研究科 生命科学専攻 【タンパク質構造論、生物物理学、生命情報学】コンピュータ・情報科学を活用し、アミノ酸配列とタンパク質の部分構造との関連を明らかにし、立体構造を予測する研究。創薬につながる。 HPへ |
おすすめ本
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。