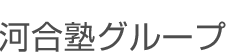「国民文学」の強いフランスでの地方文学を考える
中央集権化/地方独立の両面を生んだフランス革命

この研究は、19世紀後半から第2次世界大戦終結時までの約100年間において、ナショナリズム運動を行ったブルターニュ出身の作家、特にブルトン語とフランス語の2言語で作品の発表を行った作家たちの言動を調査することで、ブルターニュ地方の民族運動と文芸運動の関係を明らかにし、それによってこの時代のブルターニュ文学の輪郭や特徴を描き出すことを目指しています。
フランスでは、1789 年の大革命が近代国家を形成する契機となりました。身分制度が廃止され、市民の諸権利が保障されることで、普遍的な権利である人権を持つ個人が国家という共同体を形成する、という考え方が誕生しました。そしてそれは同時に、歴史や伝統に根ざした民族の共同体、という新たな概念をも生み出しました。
その結果、ナショナリズムにおいて、より強い中央集権国家を作り上げる動きと、地方において分離独立を目指す動きという相反する側面が見られるようになりました。
「国語」が国民意識や国民文学を生み出す
こうした政治的、社会的な動きは、文学にも影響を及ぼしました。フランス革命以来、中央集権・一言語主義政策がとられ、初等教育制度の成立とともに国語が急速に普及していく中で、文芸運動が国民意識や民族意識の高揚に分かちがたく結びつき、後に「国民文学」の創造を希求させるようになったのです。
その一方で地方の文学に目を転じると、そもそも地方文学という概念自体が存在しませんでした。地方文学とは、地方の作家によってその地方の風俗をテーマにしたフランス語で書かれた作品なのか、あるいは地域の言語で発表された作品なのか、常に両義性を余儀なくされてきたために、地方の多くの作品がフランス文学の中に確たる居場所を見出せない状況にありました。
さらに地方の文学には、どの言語で表現をするかという問題もありました。国内における言語統一の一環として地域語の殲滅が推し進められ、少数言語を母語とする人々もまた国語であるフランス語で作品を出版することが一般的になっていたからです。
ブルトン語が、地域ナショナリズムの基盤に
20世紀に入ると分離独立運動が進展し、それとともに地域の少数言語で書かれた文芸作品が、民族のアイデンティティの探求と結びつき、言語ナショナリズムの基盤となっていきました。この時期、ブルターニュの文芸運動は政治的な様相を帯びていきます。
ブルターニュ地方のナショナリズムは、民族を同じくする人々が同じ言語を話すという共通性に立脚していたため、地域の文学がナショナリズムの重要な柱となったのです。ナショナリズムを発展させる媒体の一つとして、文芸雑誌『グワラルン』が創刊されました。
しかしながら、第二次世界大戦下において、ブルターニュの民族運動はナチス・ドイツと関係を持っていたため、戦後、ブルターニュの地域文学はジレンマを抱えることになります。
「国文学=フランス文学」ではない文学を考える
私の今取り組んでいる研究を簡単に説明しましたが、この研究を通して「国文学(=フランス文学)」とは異なる文学について考えてみたいと思っています。
その事例としてブルターニュ地方の文学を選びましたが、それは私が約7年間にわたりこの地方に住んでいたからです。フランスにおける地方文学とはいかなるものなのか、地方文学がたどった歩みをブルターニュ地方の文芸運動を見つめることで、その答えを見つけたいと思っています。

「フランス・ブルターニュ地方における近現代の文芸運動とナショナリズム」