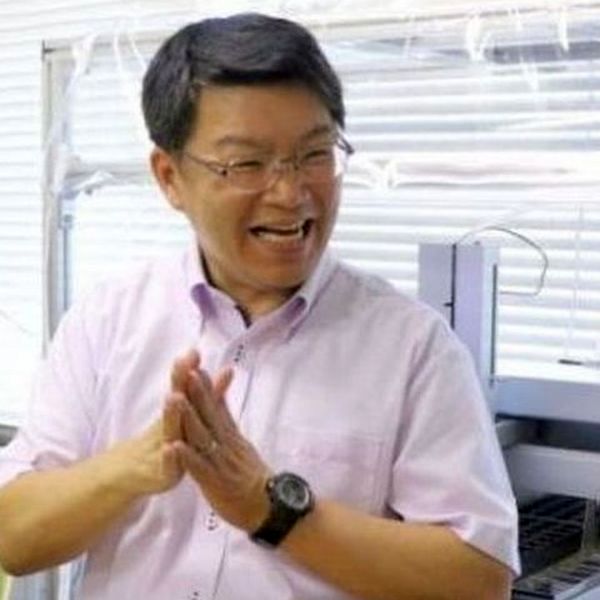学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
北海道大学理学部 生物科学科 生物学HPへ【植物発生生物学】 植物の進化・多様性や、発生メカニズムについて、最先端の研究ができる。 |
筑波大学生命環境学群 生物学類HPへ動物、植物、藻類などの系統や構造についての研究者が多く、伝統がある。前身である東京教育大学から継がれている生物学類の教育は、その授業の多様さ、きめの細かさに定評がある。 |
東京大学理学部 生物学科HPへ【生物学全般】 生物学の幅広い分野を網羅している。研究環境も国内随一といえる。 |
新潟大学理学部 理学科 フィールド科学人材育成プログラムHPへ【生殖神経内分泌学、比較内分泌学】 産卵回遊魚をモデルとした研究と魚類の脳内光受容機構に関する研究。 |
愛媛大学農学部 食料生産学科 農業生産学コースHPへ【畜産学】 鳥類ニワトリを用いて、摂食調節機構の解明を行っている研究者が在籍。 |
北里大学海洋生命科学部 海洋生命科学科HPへ【分子内分泌学】 魚類の摂食や成長、生殖を調節するペプチドホルモンの作用に関する研究。 |
日本女子大学理学部 化学生命科学科HPへ【細胞生物学】 電子顕微鏡設備が充実しており、細胞内の微細形態を観察するにはとても良い研究環境である。 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
中山剛 先生
筑波大学 生命環境学群 生物学類/理工情報生命学術院 生命地球科学研究群 【真核生物】真核生物の進化について豊富な知識を有する。独自に作成した教材も優れている。 HPへ |
 |
柴小菊 先生
筑波大学 生命環境学群 生物学類/理工情報生命学術院 生命地球科学研究群/下田臨海実験センター 【繊毛運動】多様な海産生物を研究材料として、鞭毛、繊毛の構造と機能、進化を中心とした研究を進めている。鞭毛・繊毛の美しい波形、動きを捉えるユニークなシステムに魅了されている。 HPへ |
 |
塚原伸治 先生
埼玉大学 理学部 生体制御学科/理工学研究科 生命科学専攻 【哺乳類の脳の性差に関する研究】脳の性分化に関する研究、環境化学物質の神経毒性に関する研究でアクティブに研究している。 HPへ |
 |
今野紀文 先生
富山大学 理学部 理学科 生物科学プログラム/理工学研究科 理工学専攻 【魚類と両生類の浸透圧調節機構の研究】比較内分泌学を専門に、魚類や両生類のホルモン系による恒常性の維持機構、特に魚類の淡水―海水適応などに関わる神経葉ホルモンについて研究をしている。 HPへ |
 |
松田恒平 先生
富山大学 理学部 理学科 生物科学プログラム/理工学研究科 理工学専攻/生命融合科学教育部 生体情報システム科学専攻 【魚類の摂食・情動の調節機構の研究】キンギョやゼトラフグを用いて動物の本能行動を制御する神経系ホルモンのペプチドによる摂食行動の脳制御機構を解明。さらに食欲を制御する神経ペプチドが、生殖行動や情動行動にも強い影響を及ぼすことを見出している。 HPへ |
 |
北沢美帆 先生
大阪大学 全学教育推進機構 【理論生物学】植物の形態には様々なバラツキがある。同一の植物種であっても、花びらが4枚であったり、5枚であったりする。植物のこのようなバラツキがうまれる仕組みについて理論生物学の観点から研究を行っている。従来、このようなバラツキは、厄介ものとして無視されてきたが、北沢先生は、このようなバラツキこそが植物の柔軟な形態形成の原動力であり、植物の発生において中心的な役割を果たすと提案している。 HPへ |
 |
坂本浩隆 先生
岡山大学 理学部 生物学科/環境生命自然科学研究科 環境生命自然科学専攻 【哺乳類の性行動に関する研究】世界的に有名な内海、瀬戸内海で、行動神経内分泌など生体制御学を研究。またメダカ、ラットなど脊椎動物全般のモデル生物も駆使し、分子―細胞―組織―個体―生態系を統合させて究明を行っている。 HPへ |
 |
橘哲也 先生
愛媛大学 農学部 食料生産学科 農業生産学コース/農学研究科 食料生産学専攻 【鳥類の摂食調節機構の研究】家畜の成長や生産を改善するために、動物の成長に影響を与える行動、特に摂食行動とストレスに着目して、ニワトリヒナの脳内摂食制御機構などについて研究を進めている。 HPへ |
 |
若林憲一 先生
京都産業大学 生命科学部 産業生命科学科/生命科学研究科 【クラミドモナス鞭毛】緑藻綱クラミドモナスを対象に、環境応答などとも結びつけたユニークな研究を行っている。 HPへ |
 |
上村慎治 先生
中央大学 理工学部 生命科学科/理工学研究科 生命科学専攻 【繊毛運動】科学に対する考え方も含め、たいへん丁寧に教えてくれる。研究者としても一流。 HPへ |
おすすめ本
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。