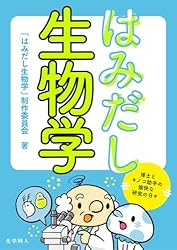サケは、大洋から川にかけて大きく変化する海洋環境に適応しながら回遊し、十分成熟した後に自分が生まれた母川に回帰し産卵します。また、クサフグは春から夏にかけて2週間に1回、新月と満月の日の満潮前に海岸の一角に集合し産卵します。このような産卵回遊は、フィールドにおける複合的な環境要因への適応として、さまざま生理機能や行動が連動して起こる生物現象です。私はこれまで、サケ科魚類やフグ科魚類などの回遊魚を研究対象として、動物の環境適応を調節する体のしくみについて研究してきました。
魚類は様々な産卵リズムを持っています。それは、光や温度などの環境要因と、脳の間脳という部位にある神経内分泌系から分泌される様々な神経ホルモンによって調節されていると考えられています。私はとりわけ、生殖リズムや季節繁殖を調節している脳神経機構を明らかにしようと取り組んでいます。そのためにクサフグを用いて、半月周性(2週間周期)の産卵リズムをきざむ生物時計が脳のどのような場所ではたらいているのか調べています。
生殖リズムや季節繁殖を調節している脳神経機構が明らかになれば、生殖機能不全の治療法の開発や、効率的な生物資源の生産や保全につながると考えています。


研究対象であるクサフグを採集しているところ
一般的な傾向は?
- ●主な業種は→薬品、食品、飲料、醸造、水産、畜産、農業、教育、博物館、水族館、商業、電機、IT、印刷など
- ●主な職種は→研究、開発、プロパー、営業、公務員、教員など
分野はどう活かされる?
県公務員(水産)、薬品会社の研究員、食品会社の研究員、水族館の飼育員、高校や中学校の理科教員として活躍しています。
生命現象は調べれば調べるだけ、また新しい謎が出てきます。未知の領域に向かって歩んでいく好奇心と情熱、大胆さ、そして忍耐力を持って、一歩先に足を踏み出して、生命の不思議を探検する旅に出てみましょう。きっと新しい何かが見えてくるはずです。
新潟大学佐渡自然共生科学センター臨海実験所では、美しい海と豊かな生物相を持つ佐渡島において、海洋生物の多様性とその成り立ちについての研究を進めています。
理学科生物学プログラムでは、分子から細胞、個体レベルの生命現象を幅広く学ぶことができます。また、理学科フィールド科学人材育成プログラムは、理学部と農学部の教員が協働する教育プログラムで、生態学、環境動態、災害科学を中心に様々さまざまなフィールド科学を学ぶことができます。

興味がわいたら~先生おすすめ本

小鳥はなぜ歌うのか
小西正一
著者は小鳥のさえずりに関する研究の第一人者で、フクロウの聴覚を観察することで動物行動学と大脳生理学を結合させたことで知られる。小鳥はなぜ鳴くのか。天敵の気配を察知すると警戒鳴き、縄張り争いから、恋のささやきまでエピソードを中心に説明し、小鳥の歌の研究からみた人間の心理まで話は及んでいる。 (岩波新書)