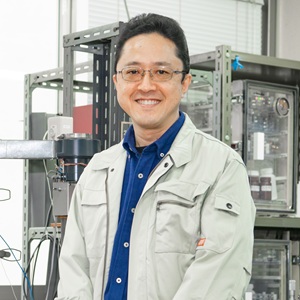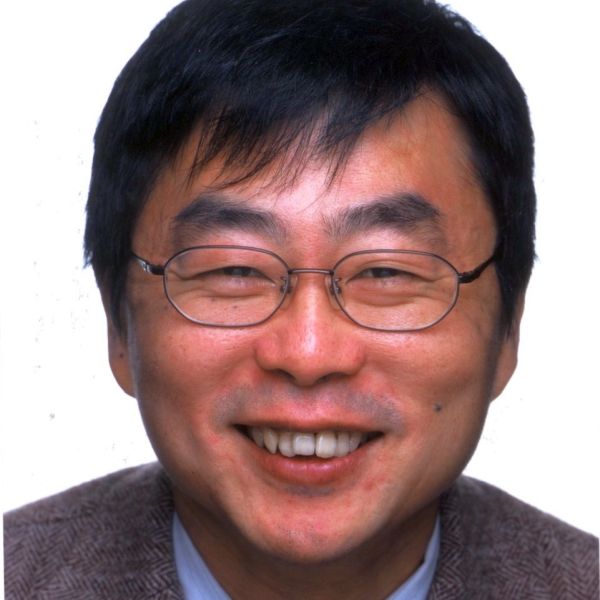学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
北海道大学工学部 情報エレクトロニクス学科HPへ【システム情報科学】 電気制御システムコースでは、身の回りの様々なシステムを設計するために、電気、情報科学、システム科学を融合した新技術を研究している。ロボット、工場、街など様々な対象をモデル化し、新しいシステムを創るための研究ができる。 キャンパスの風景も素晴らしい。 |
東京大学工学部 精密工学科HPへ【精密工学】 精密工学科では、ソフトウェアからハードウェアまで幅広く学べるのが特徴!異なる分野が融合したテーマの研究もできるので、色々なことをしてみたい人におすすめできる。広い視点を持ち、他の分野にも興味を持つ姿勢が身につく。 |
愛知教育大学教育学部 学校教員養成課程 義務教育専攻 教科指導系 理科専修HPへ【トライボロジー】 原子スケールの摩擦の研究 |
京都大学工学部 物理工学科 機械システム学コースHPへ【最適設計】 トポロジー最適化の研究で世界的にも注目されている。 |
千葉工業大学工学部 機械電子創成工学科HPへ【トライボロジー】 興味を持って現象を明らかにしようとする姿勢がある。 |
中央大学理工学部 情報工学科HPへ【数理情報学】 社会の様々な課題を、数学や論理を武器に解決する方法を研究している先生が多数在籍。コンピュータ処理技術の教育も充実している。計算幾何学やコンピュータグラフィクスに強い先生方が揃っているのも魅力である。数学が好きな人、数理的な手法で研究をしたい人に特におすすめ。 |
同志社大学理工学部 機械システム工学科HPへ【潤滑現象の基礎的解明】 ナノスケールでの流体の特性に関する研究。 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
成田幸仁 先生
室蘭工業大学 理工学部 創造工学科/工学研究科 生産システム工学系専攻 【伝動装置の効率と負荷容量向上】無段変速機、または連続可変トランスミッションともいうCVTを中心に、車や工作機械の伝動装置について綿密な研究を行っている。 HPへ |
 |
足立幸志 先生
東北大学 工学部 機械知能・航空工学科 機械システムコース/工学研究科 機械機能創成専攻 【摩擦摩耗、トポロジー】表面・接触面における摩擦の科学と技術、トライボロジーを基盤とした機械設計を行う。 HPへ |
 |
寒野善博 先生
東京大学 工学部 計数工学科 数理情報工学コース/情報理工学系研究科 数理情報学専攻 【最適化法】数理最適化のモデリング、解法とその設計力学への応用研究で質の高い研究論文を出しており、国際的にも注目されている。 HPへ |
 |
大竹豊 先生
東京大学 工学部 精密工学科 【形状モデリング】もともとコンピュータグラフィクスの研究で世界的に有名な先生で、研究成果の画像がいつも魅力的。ものづくりに役立つ3次元形状処理に関して幅広く扱っており、ダイナミックな発想の研究ができる。 HPへ |
 |
鈴森康一 先生
東京科学大学 工学院 機械系 【人工筋肉】人工筋肉とソフトロボティクス研究で、人工筋の開発とロボット応用を進めており、分野の第一人者。 HPへ |
 |
茅原崇徳 先生
金沢大学 理工学域 フロンティア工学類/自然科学研究科 機械科学専攻/新学術創成研究機構 【人間工学】人間工学の中に最適化を持ち込み、今後、注目されるであろう研究を行っている。 HPへ |
 |
本田知己 先生
福井大学 工学部 機械・システム工学科 機械工学コース/工学研究科 産業創成工学専攻 【トライボロジー】微細形状と摩擦力の検討。 HPへ |
 |
福澤健二 先生
名古屋大学 工学部 機械・航空宇宙工学科/工学研究科 マイクロ・ナノ機械理工学専攻 【マイクロナノ計測】計測技術の開発とトライボロジー計測への応用。 HPへ |
 |
梅原徳次 先生
名古屋大学 工学部 機械・航空宇宙工学科/工学研究科 マイクロ・ナノ機械理工学専攻 【トライボロジー、炭素系硬質薄膜】摩擦を扱うトライボロジー研究で、自動車エンジン内部および駆動系における摩擦によるエネルギーの伝達ロス、パソコンのハードディスクの耐久性を向上させるためディスク表面に潤滑保護膜を作る摩擦まで考察し、また炭素系硬質薄膜の超低摩擦について、特徴的な研究を行っている。 HPへ |
 |
大崎純 先生
京都大学 工学部 建築学科/工学研究科 建築学専攻 【最適設計法】最適設計法で質の高い研究論文を出している HPへ |
 |
平山朋子 先生
京都大学 工学部 物理工学科 機械システム学コース/工学研究科 機械理工学専攻 【潤滑現象の基礎的解明】トライボロジーの観点から機械要素の潤滑挙動についてマイクロパターンと流体潤滑を調べる詳細な研究を行っている。 HPへ |
 |
西脇眞二 先生
京都大学 工学部 物理工学科 機械システム学コース/工学研究科 機械理工学専攻 【最適設計法】トポロジー最適化の権威。 HPへ |
 |
小森雅晴 先生
京都大学 工学部 物理工学科 機械システム学コース/工学研究科 機械理工学専攻 【ロボットメカニズムの創造とデザイン】ロボットメカニズムから多段変則できるパワートランスミッションまで幅広く研究している。 HPへ |
 |
脇元修一 先生
岡山大学 工学部 工学科 機械システム系/環境生命自然科学研究科 【アクチュエータ工学、ソフトメカニズム】柔らかい材料で作るアクチュエータの研究。高い安全性を持ち、人間の体に接する必要のある医療用ロボットや福祉ロボット、農作物などの壊れやすく大きさも異なる作物になじみながら動くロボットハンドを作ることを可能にする。 HPへ |
 |
黒河周平 先生
九州大学 工学部 機械工学科/工学府 機械工学専攻 【機械要素部品の超精密加工、計測技術】機械要素部品の超精密加工、計測技術に関して、実機械要素の性能の観点から研究している。 HPへ |
 |
中村太郎 先生
中央大学 理工学部 精密機械工学科/理工学研究科 精密工学専攻 【人工筋肉】ユニークなロボットを多く開発している。 HPへ |
 |
森口昌樹 先生
中央大学 理工学部 情報工学科 【幾何形状処理】コンピュータ上で3次元の形を扱うアルゴリズム(幾何形状処理)について、基礎から最先端の技術まで、豊富な知識で研究している。数理論理にもコンピュータ技術にも強い先生なので、数学のしっかりした論理を使って研究したい人におすすめである。 HPへ |
おすすめ本
「科学」2023年7月号(特集 Origamiの可能性)
石田祥子ほか
折紙研究に関する特集「Origamiの可能性」が掲載されています。
折紙研究と言っても、日本の大学に折紙学部や折紙学科があるわけではありません。折紙という独立した学問があるのではなく、「折紙を活用した製品や建築物」であれば工学系、「折紙をデザインするプログラミングやソフトウェア」であれば情報科学系、「数学的記述をもちいて折紙の本質にせまる」のであれば数学系、「折紙の芸術的価値や創作」であれば芸術系といったように、幅広い分野の専門家がそれぞれの視点で折紙の研究を行っていますので、折紙の何を勉強したいのかによって選ぶ学部・学科は変わってきます。
この特集記事にはさまざまな分野の専門家が関わっていますので、進路選択の一助になるのではと思います。
(岩波書店)
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。
海外で学ぶなら
Ohio State University/オハイオ州立大学(米)HPへMechanical and Aerospace Engineering HPへ【Gear and power transmission systems applications】 米国で有数のトランスミッションに関する研究グループがある。 |
University of Sheffield/シェフィールド大学(英)HPへDepartment of Mechanical Engineering HPへTribology Center(研究所)がある。英国で上位の研究を行っており、Asia圏からの留学生も多い。 |
Uppsala University/ウプサラ大学 (スウェーデン)HPへオングストローム研究所 HPへ【トライボロジー】 トライボロジー全般、薄膜等、トライボロジー材料の科学・技術に対して高度な研究を展開。 |
Curtin University/カーティン大学(豪)HPへDepartment of Mechanical Engineering HPへ【Tribology Laboratory Science and Engineering】 豪州のトライボロジー研究の中心的役割を担っている。Asia圏から留学生の受入れも多い。 |