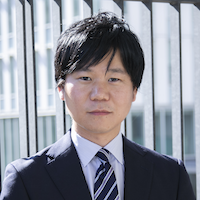学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
東北大学医学部 医学科 /包括的脳科学研究・教育推進センターHPへセンターは、医学薬学・理学・工学・人文科学など多領域の研究教育スタッフが協力して脳科学に取り組む研究所。高校生向けに種々の企画も行っている。 |
千葉大学医学部 医学科 /予防医学センターHPへ【環境生命医学】 予防医学センターは、子どもの発達と環境に関する大規模な縦断的調査を実施している国内でも数少ない研究施設の一つである。 |
富山大学医学部 医学科HPへ【精神医学】 |
広島大学医学部 医学科HPへ【精神神経医科学】 脳機能画像解析に加えて、ゲノム解析や網羅的な蛋白質解析等、多角的に精神疾患に関する研究を行っている。日本を代表する精神医学教室。 |
名古屋市立大学医学部 医学科HPへ【精神医学】 |
慶應義塾大学医学部 医学科HPへ【精神医学】 |
帝京大学医学部 医学科HPへ【精神医学】 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
福田正人 先生
群馬大学 医学部 医学科/医学系研究科 生命医科学専攻 【精神医学、脳機能画像、臨床神経生理学、思春期学】脳の機能と関連づけの中で、人間の心や精神について、一人ひとりが充実した生活と人生を送ることを科学の視点から支援する研究。 HPへ |
 |
笠井清登 先生
東京大学 医学部 医学科/医学系研究科 脳神経医学専攻 【精神医学】一般人口における精神疾患の生涯有病率は46%と言われる。そんな背景から、自閉症や体内リズムなどに関わる脳内機構を分子レベルで解明していく最先端の研究者。 HPへ |
 |
山末英典 先生
浜松医科大学 医学部 医学科/医学系研究科 医学専攻 【精神医学】脳機能イメージング、遺伝子解析など多彩な手法を駆使して、様々な角度から発達障害の病因解明、治療法開発に取り組んでいる。 HPへ |
 |
村井俊哉 先生
京都大学 医学部 医学科/医学研究科 医学専攻 【精神医学】臨床研究に力点を置く伝統を引き継ぎながら、神経画像技術など新規の研究手法も柔軟に取り入れている。 HPへ |
 |
三村將 先生
慶應義塾大学 医学部 医学科/医学研究科 医科学専攻/医学部 予防医療センター 【精神医学】 HPへ |
 |
菊水健史 先生
麻布大学 獣医学部 動物応用科学科/獣医学研究科 動物応用科学専攻 【伴侶動物学】人とペットなどの動物との絆や動物のこころ、社会認知などについてユニークな研究を展開。 HPへ |
 |
佐藤弥 先生
理化学研究所 【脳機能イメージング】自閉症患者の社会性障害をもたらす神経基盤に関して質の高い研究成果を挙げている。 HPへ |
おすすめ本
つながる脳科学 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線
理化学研究所
神経細胞の構造の記述から始まった脳研究は、現代では、画像研究、分子生物学研究、人工知能など、様々な視点から進められています。この本では、日本における脳研究者の第一人者たちが、それぞれ自分の強みを生かして、記憶を操ることはできるのか、心の病気は治せるのか、などといった難問に挑戦していく、その試みの一端を伺うことができます。
精神疾患は脳が原因臓器であると考えられていますが、まだ詳しいことがほとんどわかっていない、これからの研究分野です。脳科学に興味を持ち、精神疾患研究の分野に、どんな方向からであれ、若い力が参入してくれることを願ってやみません。
(脳科学総合研究センター)
脳には妙なクセがある
池谷裕二
脳は見たり聞いたりしたことを瞬時に理解し、次にどのような行動を取るべきかを判断している。脳内でどのようなことが起こっているかは不明な点は多いのだが、最近明らかになってきた脳の不思議な活動が述べられている。例えば、恋をすると脳の処理速度が早くなる話、寝ている間に記憶が定着する話、言語を獲得するきっかけとなった遺伝子の話など。筆者は周囲の環境から受ける刺激とそれに対する反応行動が基になり心が形作られてきたと考察している。これまで哲学や心理学といった文系領域で取り扱われてきた脳の働きや精神活動も、今後生物学的な知見に基づいて理解されることにより、精神疾患に対する新たな治療法が開発されると期待される。 (扶桑社新書)
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。
海外で学ぶなら
Emory University/エモリー大学(米)HPへDepartment of Psychiatry and Behavioral Sciences HPへプレリーハタネズミを用いた社会性に関する研究で世界のトップを走るLarry Young博士が在籍。 |
Università degli Studi di Trento/トレント大学(伊)HPへ【認知科学】 臨床・基礎が一体となった精神疾患研究が展開されている。 |