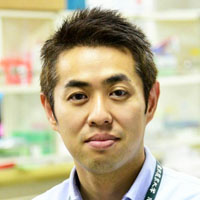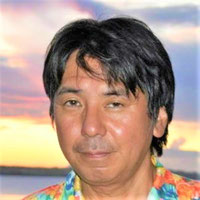学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
北海道大学農学部 生物機能化学科HPへ肥満と腸内細菌の関係について、興味深い研究を行っている。 |
東京科学大学生命理工学院 生命理工学系HPへ生物機能を体系的に捉え、応用へもアプローチしている。 |
東京農工大学工学部 生命工学科HPへ【応用微生物学】 磁石を持つ微生物の研究。 |
大阪大学工学部 応用自然科学科HPへ最先端のバイオテクノロジーを学ぶことができる。国際交流も盛んに行っている。 |
神戸大学農学部 生命機能科学科 応用生命化学コースHPへ【微生物機能化学】 |
広島大学工学部 第三類(応用化学・生物工学・化学工学系)HPへ応用微生物学分野をリードする優秀な研究者が多く在籍している。 |
山口大学農学部 生物機能科学科 /中高温微生物研究センターHPへ中高温微生物研究センターがあり、発酵微生物だけでなく、環境微生物、病原微生物に関する研究部門からなり、統合的に微生物を理解しようと研究に取り組んでいる。 |
秋田県立大学生物資源科学部 応用生物科学科HPへ【共生細菌】 昆虫や植物、ヒトや家畜などと細菌との共生関係を研究している。同学部の生物環境科学科では、微生物を利用して廃水や環境の浄化の研究を行っている。 |
北里大学薬学部 /北里生命科学研究所HPへ【放線菌のゲノム工学】 北里生命科学研究所では、世界有数、おそらくトップの放線菌を用いた代謝工学を行っている。ノーベル賞学者大村先生の直系である。 |
慶應義塾大学環境情報学部 環境情報学科 /先端生命科学研究所HPへ【ゲノム工学】 世界最大の巨大DNAクローン技術を持ち、独自性ではトップクラス。 |
日本大学生物資源科学部 バイオサイエンス学科HPへ発酵など、微生物利用を志す研究者が多く所属し、教育を行っている。学生からの評判も良い。 |
奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 先端科学技術専攻 バイオサイエンス領域HPへ【システム微生物】 Systems biologyを用いた生命現象の理解をめざしている。大腸菌研究では日本のトップである。 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
天知誠吾 先生
千葉大学 園芸学部 応用生命化学科/園芸学研究科 環境園芸学専攻 【微生物工学】ヨウ素、ヒ素、アンチモン、バナジウムなどの元素を使って呼吸をする嫌気呼吸細菌について、分子レベルで調べ、応用にも取り組んでいる。 HPへ |
 |
中根大介 先生
電気通信大学 情報理工学域 Ⅲ類(理工系) 化学生命工学プログラム/情報理工学研究科 基盤理工学専攻 【微生物の運動】微生物の見せる面白い運動(動き)を独自の技術を駆使して観察し、その仕組みを解き明かしている。 HPへ |
 |
寺田昭彦 先生
東京農工大学 工学部 化学物理工学科 【環境バイオエンジニアリング】微生物の働きによる水からの窒素の除去や、温室効果ガスである亜酸化窒素の発生について詳しく調べている。 HPへ |
 |
小川順 先生
京都大学 農学部 応用生命科学科/農学研究科 応用生命科学専攻 【発酵生理及び醸造学】自然現象を素直に観察して、洞察を得た上で、理解と問題解決を図る手順がすばらしい。企業との共同研究が多く、「出口に近い」研究を展開。 HPへ |
 |
吉田健一 先生
神戸大学 農学部 生命機能科学科 応用生命化学コース/科学技術イノベーション研究科 科学技術イノベーション専攻 【微生物を利用した稀少物質生産】高い組換え能を有する細菌を効果的に利用。 HPへ |
 |
藥師寿治 先生
山口大学 農学部 生物機能科学科/創成科学研究科 農学系専攻/中高温微生物研究センター 【微生物の生化学、代謝工学】バクテリアのべん毛モーターについての研究。細胞内外で発生する電気ポテンシャルで回転するべん毛モーターのエネルギーは、どうやって作り出されるのか、エネルギー代謝について調べている。 HPへ |
 |
朝井計 先生
東京農業大学 生命科学部 バイオサイエンス学科/生命科学研究科 バイオサイエンス専攻 【細胞分化の誘導機構】細胞の環境応答と生存戦略の分子機構を解明し、合成生物学的手法の応用的な実践する。 HPへ |
 |
高松大輔 先生
農業・食品産業技術総合研究機構 【ミツバチ腐蛆病予防】腐蛆病というミツバチの幼虫を侵す伝染病がある。家畜伝染病予防法における法定伝染病である。この疾病を引き起こす病原菌の多様性を明らかにしている。 HPへ |
 |
横田篤 先生
北海道大学 農学部 生物機能化学科/農学院 農学専攻 生命フロンティアコース 【アミノ酸発酵】発想がユニーク。研究内容は丁寧で説得力がある。 HPへ |
おすすめ本
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。
海外で学ぶなら
University of California, Berkeley/カリフォルニア大学バークレー校(米)HPへ化学工学・生物工学 HPへ【バイオ燃料生産のための合成生物学】 バイオ燃料に関する研究では世界を先導している。 |
University of Houston/ヒューストン大学(米)HPへDepartment of Biology and Biochemistry HPへ【Synthetic Biology】 枯草菌の胞子形成を量的制御の視点から細胞分化の分子機構を目指す。 |
University of Newcastle/ニューカッスル大学(英)HPへInstitute for Cell and Molecular Biosciences HPへ【Bacterial Cell Biology】 進化的視点を踏まえた斬新的な微生物学を先導。 |