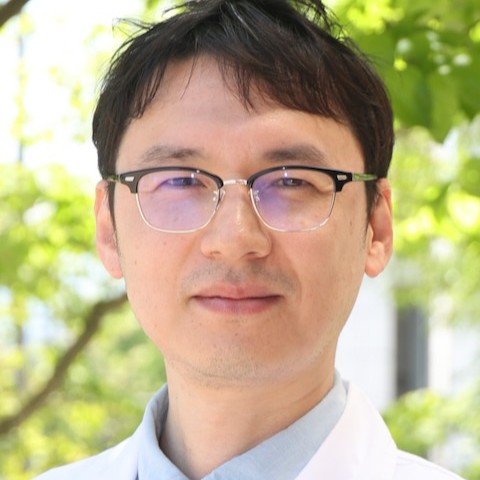学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
筑波大学理工学群 物理学類HPへ【生命量子化学】 重田育照先生の生命物理研究グループは、生体内現象を分子レベルで理論解析し、生命の根本原理を解明する研究を行う。 |
群馬大学理工学部 物質・環境類HPへ【光化学】 地方大学の中では、物理化学をベースとした光化学の研究が広範な領域にわたっている。絶対蛍光量子収率測定装置の開発、蛍光プローブ、光による結晶成長など。 |
金沢大学理工学域 フロンティア工学類HPへ【原子間力顕微鏡、固液界面の局所物性の解析技術】 福間剛士先生は、原子間力顕微鏡を固液界面に適用する技術開発を世界に先駆けて行って来た研究者であり、独自技術を開発しながら界面物性の精密測定に挑んでいる。 |
名古屋大学理学部 化学科HPへ【放射光を用いた触媒の局所解析による機構解明、フェムト秒レーザー】 唯美津木先生は、微細な構造と不均一な分布をもつ触媒の一つ一つを選別しながら解析する、放射光を用いた解析技術で世界をリード。菱川明栄先生はフェムト秒レーザーを用いた新しい反応顕微鏡を開発し、反応している分子の動画撮影を目指している。 |
名古屋大学情報学部 自然情報学科HPへ【液体の統計力学理論、生体分子機能の解明】 世界的には生体内過程、生体分子機能の理論的扱いには分子動力学法が用いられているが、吉田紀生先生たちのグループでは視点を変えて、液体の統計力学理論によるアプローチを行っている。 |
岡山大学理学部 化学科HPへ【水の研究】 水の研究者が集まっている。 |
広島大学工学部 第二類(電気電子・システム情報系) 電子システムプログラムHPへ生体物質を磁場への応答性によって解明。 |
愛媛大学理学部 理学科 地学コースHPへ【高圧下の氷とハイドレート】 学内にある地球深部ダイナミクス研究センターは、高圧実験に特化した研究機関。氷の結晶構造は、高圧では10種類以上にもなり、それぞれがユニークな性質を持つ。これらの氷は外惑星やその衛星に存在するが、地球上で実験するなら高圧装置が必要なのだ。 |
九州大学工学部 応用化学科HPへ【生命量子化学機能材料設計】 吉澤一成先生は、量子力学の原理に基づいて「分子と固体の電子物性」、「酵素化学反応」などの最先端の研究課題に取り組む。 |
青山学院大学理工学部 化学・生命科学科HPへ【物理化学、機能物性化学】 光化学を中心に、物理化学、機能性材料化学、錯体化学等広範にわたる研究室がある。 |
慶應義塾大学理工学部 化学科HPへ【触媒表面のオペランド観測による機構解明】 近藤寛先生は、触媒反応が進行する界面を、シンクロトロン(加速器)施設において放射光を用いて解析するユニークな手法を開発し、解析を進めている。 |
早稲田大学先進理工学部 応用物理学科HPへ【アト秒物理】 アト秒レーザーという非常に短い時間だけ発するレーザーを使って、分子内の電子の動きを実験的に可視化する手法の開発を進めている。 |
早稲田大学先進理工学部 化学・生命化学科HPへ【相対論的量子化学、大規模系の量子化学】 中井浩巳先生は、原子・分子の性質を司る電子の運動を理論的に解明する「理論化学」に取り組む。 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
伊藤肇 先生
北海道大学 工学部 応用理工系学科 応用化学コース/総合化学院 総合化学専攻 【有機金属化学】物理化学分野の研究者ではないが、有機金属化学から合成し、発見した結晶相転移現象に関して多くの研究成果を報告している。 HPへ |
 |
奥津哲夫 先生
群馬大学 理工学部 物質・環境類 応用化学プログラム/理工学府 理工学専攻 【光物理化学】タンパク質の光誘起結晶化のパイオニア。物理化学をベースに結晶生成過程を研究している。 HPへ |
 |
吉田紀生 先生
名古屋大学 情報学部 自然情報学科/情報学研究科 複雑系科学専攻 【液体の統計力学理論】人の体は水が約60%、40%がタンパク質などの生体高分子で占める。水溶液中の統計力学の理論を用いタンパク質などの生体分子が、どのように薬剤分子と相互作用するかを、コンピュータを使って予測する。 HPへ |
 |
松田建児 先生
京都大学 工学部 理工化学科 先端化学コース/工学研究科 合成・生物化学専攻 【機能物性化学】有機合成の手法を駆使して分子を合成し新規の有機機能性材料を開発し、分子ナノテクノロジーの開拓を目指す。個体ー液体の界面での光応答分子の挙動について研究している。 HPへ |
 |
岩坂正和 先生
広島大学 工学部 第二類(電気電子・システム情報系) 電子システムプログラム/ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 【生体関連の磁気科学】魚が太陽光を高効率に利活用するしくみをまねるバイオミメティックスを実現し、その技術を光デバイス、新しい光制御技術に役立てるイノベーションに挑む。独創性が高い。 HPへ |
 |
朝日剛 先生
愛媛大学 工学部 工学科 化学・生命科学コース/理工学研究科 物質生命工学専攻 【物理化学・分析化学】有機ナノ結晶の光物理化学で有名。 HPへ |
 |
深港豪 先生
熊本大学 工学部 材料・応用化学科/自然科学教育部 材料・応用化学専攻 【機能物性化学】日本での単一分子観測の先駆け的な研究者。最近では非線形光応答システムの構築を行っている。 HPへ |
 |
小畠誠也 先生
大阪公立大学 工学部 化学バイオ工学科/工学研究科 物質化学生命系専攻 【機能物性化学】光の照射で変色する性質を持つフォトクロミック分子の光誘起結晶形態変化の研究で有名。 HPへ |
 |
岡島元 先生
中央大学 理工学部 応用化学科 【ラマンイメージング、分子分光学】光を照射すると生じる散乱光の中で、入射光とは異なる波長に散乱されるラマン散乱の分光法を研究する。低振動数のラマン分光から、分子間相互作用について検討している若手研究者。 HPへ |
おすすめ本
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。
海外で学ぶなら
University of Alberta/アルバータ大学(カナダ)HPへ【液体の統計力学理論に基づくナノ/バイオ分子の溶媒和に関する理論的研究】 生体分子系、ナノマテリアル系への応用を行っている。 |
Goethe University Frankfurt/ゲーテ大学フランクフルト(独)HPへ核物理研究所 HPへ【原子分子物理学】 世界中で普及している反応顕微鏡(COLTRIMS)の開発元で、最先端の原子分子物理学研究を進めている。 |
厦門大学(中)HPへState Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces HPへ【ナノ合成化学、触媒化学】 固体表面や物理化学を足場として、物質科学や触媒化学に関して世界トップレベルの研究を繰り広げている。 |
国立陽明交通大学(台)HPへ【化学全般】 日本の有名な国立大学を定年退職された教授陣が数多く在籍している。杉山輝樹副教授は、レーザートラッピングによる結晶生成の研究を進めている。日本人がいることから、安心な面もある。 |
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg/フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン=ニュルンベルク(独)HPへドイツの中でも治安や環境もよく、物理化学には優秀な研究者が揃っている。 |
中国科学技術大学(中)HPへ近代物理学科 HPへ【反応動力学】 世界で2台目の時間分解(ナノ秒)電子運動量分光装置を現在開発中である。 |