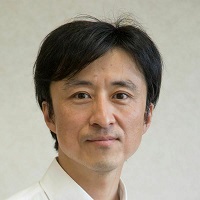学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
宇都宮大学農学部 森林科学科HPへ【森林科学】 森林に関する技術者を育てるための技術士(JABEE)プログラムを設定し、体系的な教育を行っている。 |
静岡大学農学部 生物資源科学科 木質科学コースHPへ【抽出成分、木質材料】 |
岐阜大学応用生物科学部 応用生命科学課程 分子生命科学コースHPへ【抽出成分】 |
東京農業大学地域環境科学部 森林総合科学科HPへ【きのこ】 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
大山幹成 先生
東北大学 理学部 生物学科/生命科学研究科 生態発生適応科学専攻/植物園 【樹木年輪を用いた古気候復元および木質遺物の年代同定】樹木年輪を用いた気候復元のみならず,遺跡からの出土品の樹種同定や年代同定を行い、考古学的な分野においても活躍している。 HPへ |
 |
山田利博 先生
東京大学 農学部 応用生命科学課程 森林生物科学専修/農学生命科学研究科 森林科学専攻/演習林 【樹病】 HPへ |
 |
奈良一秀 先生
東京大学 新領域創成科学研究科 自然環境学専攻 【自然生態系における菌根共生】菌根の姿を通して森林生態系を解き明かそうとしている。 HPへ |
 |
山田明義 先生
信州大学 農学部 農学生命科学科 生命機能科学コース/総合理工学研究科 農学専攻 【菌根性キノコの発生機構の解明】マツタケをはじめ培養が困難なキノコを形成する菌根菌に関する研究を進めている。 HPへ |
 |
中塚武 先生
名古屋大学 理学部 地球惑星科学科/環境学研究科 地球環境科学専攻 【気候変動に対する社会応答の歴史的関係の解明】古気候学や気候学などの理系分野の研究者はもちろん、歴史学や考古学などの文系分野の研究者とともに、多分野横断型のプロジェクト研究を主宰している。 HPへ |
 |
斎藤琢 先生
岐阜大学 応用生物科学部 生産環境科学課程 環境生態科学コース/流域圏科学研究センター 【常緑針葉樹林における物質循環研究】森林全体の水、熱、炭素収支を測定するフラックス観測研究にあたり、最も精力的に研究を行い、論文執筆やデータ公開を進めている。また異分野研究者との交流を積極的に進め、将来的に学際的研究のハブとなることが期待される。 HPへ |
 |
檀浦正子 先生
京都大学 農学部 森林科学科/農学研究科 森林科学専攻 【樹木根をめぐる森林炭素動態】森林の炭素循環を明らかにするため、特に根圏に着目して炭素循環プロセスを明らかにする実験を行っている。炭素安定同位体をトレーサーとして用いる研究の第一人者として注目されている。フィールドは、国内に留まらず、フランス、熱帯および亜寒帯林に達する。 HPへ |
 |
米延仁志 先生
鳴門教育大学 学校教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教育専修・中学校教育専修 技術科教育コース/学校教育研究科 高度学校教育実践専攻 【古環境変動の復元】樹木年輪や湖底堆積物に同位体など様々な指標を用いた古環境変動の復元に取り組んでいる。 HPへ |
 |
佐野雅規 先生
国立歴史民俗博物館 【樹木年輪を用いた気候復元】将来予測のための気候モデルの改良にあたり、最も求められている研究の一つが過去の気候復元である(IPCC第五次報告書)。年輪を用いた気候復元において、現在国内で最も精力的に研究を行いデータを出している研究者。 HPへ |
おすすめ本
森林飽和 国土の変貌を考える
太田猛彦
森林科学科に入学する新入生の多くは自然に対するあこがれを抱いている。「身近で森林伐採が行われていたから森林破壊を防止したい」という志望動機を持っている場合が多い。しかしこの本はこれとはまったく逆のことを訴える。国挙げての植林活動の結果、これ以上その必要性がないほど、いまや日本の森林は飽和状態だというのだ。すなわち、今現実に日本で起きているのはまったく違う問題であることに気がつかせてくれる。森林を学ぶにあたり、ステレオタイプな考えかたでなく、保全・保護の観点、利用の観点、共生の観点など、さまざまな立場からの新しい視点で捉えられると理解が深まる。また、その複雑さが森林科学の魅力であると思われる。 (NHKブックス)
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。
海外で学ぶなら
North Carolina State University/ノースカロライナ州立大学(米)HPへ環境資源学部 森林・環境資源学科 HPへ【樹木バイオテクノロジー】 |
University of British Columbia/ブリティッシュコロンビア大学(カナダ)HPへ森林学部 HPへ【森林科学一般】 |