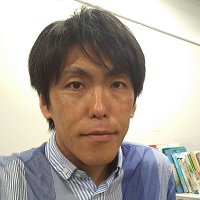学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
宮城教育大学教育学部 学校教育教員養成課程 初等教育専攻 理数・自然系教育創生コース/中等教育専攻 理数系教育コースHPへ【動物発生学】 様々な海産動物の受精メカニズムに着目した多様性について、勢力的に研究を行っている。 |
東京科学大学生命理工学院 生命理工学系 /地球生命研究所HPへ【人工細胞】 進化の研究の最終目標の一つは、進化の仕組みを応用し、人類に役に立つものを作ること。この目的のために、人工的な細胞を実験的に進化させて、進化の原理を明らかにしようとする研究が行われている。生物進化の再構築を目指す野心的で新しいアプローチの研究である。 |
大阪大学工学部 応用自然科学科 バイオテクノロジー学科目HPへ醸造・醗酵の歴史を組むバイオテクノロジー。進化も含む多様な生命科学分野における応用研究を行っている。 |
島根大学生物資源科学部 生命科学科 細胞生物学コースHPへ【進化生物学】 ミドリゾウリムシを使用した二次共生の研究では世界をリードしている。具体的には、ミドリゾウリムシの感染ルートの詳細の解明、細胞内共生維持のための遺伝子の探索、細胞内共生前と後の宿主とクロレラの行動の変化を研究している。 |
広島大学理学部 生物科学科HPへ【半索動物の分子発生学的研究】 ヒトなどの脊索動物と類縁する、半索動物を用いたゲノム解析や発生過程での遺伝子解析を行う。臨海実験所があり、海産動物を研究するには非常に魅力的な場所で研究を行うことができる。半索動物を用いた研究において、世界を代表する研究室である。 |
山口大学理学部 生物学科HPへ【昆虫の季節・環境適応の内分泌学的研究】 チョウの翅や蛹の体色は、周囲の環境に応じて変化するが、世界に先駆けて、チョウの色彩変化を誘導するホルモンを2種類発見した。身近なチョウを題材に、古典的実験手法から分子生物学を駆使し、「生物」学を実感できる教育・研究を展開している。世界的にもユニークな研究室であり、山口大学周辺の自然環境が研究環境を与えている。 |
京都府立大学農学食科学部 農学生命科学科HPへ【複合適応形質の進化研究】 動物-植物間の相互作用については、分子機構がよくわかっていない面白現象が多く存在している。草食性の虫によって形成される植物の「虫こぶ」もその一つ。京都府立大には「虫こぶ」を異種操作能というユニークな観点から、研究している面白い研究室がある。 |
東京薬科大学生命科学部 応用生命科学科HPへ【生命初期進化の研究】 最初の生命はどのようなものであったかという問いかけは、今なお生物学の、もっとも大きな謎の一つで、どのような研究手法がよいのかもわかっていない。東京薬科大学には、極限環境での生命現象や分子機構の解析から、この謎を解き明かそうとする挑戦的な研究室がある。 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
美濃川拓哉 先生
東北大学 理学部 生物学科/生命科学研究科 生態発生適応科学専攻/浅虫海洋生物学教育研究センター 【進化発生学】ウニ類を用いた個体発生メカニズムの進化や、細胞の多分化調節能について研究を行っている。 HPへ |
 |
日比野拓 先生
埼玉大学 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース・小学校コース 自然科学専修 理科分野/教育学研究科 教職実践専攻 【進化発生学、比較免疫学】ウニやヒトデなどの棘皮動物のボディープランの進化や、免疫機構の進化について研究を行っている。 HPへ |
 |
松浦友亮 先生
東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系 生命理工学コース/地球生命研究所 【人工細胞】 HPへ |
 |
児玉有紀 先生
島根大学 生物資源科学部 生命科学科 細胞生物学コース/自然科学研究科 農生命科学専攻 【ミドリゾウリムシを使った二次共生の成立機構の研究】ミドリゾウリムシークロレラの二次共生研究をする。ミドリゾウリムシにパルス的に1.5分だけクロレラを宿主の食胞に取り込ませてその後の運命を追跡する技術開発に成功。クロレラが共生するための感染ルートの全容を明らかにした。現在、遺伝子情報も使えるようになり、ミドリゾウリムシは二次共生の成立機構解明のモデル材料になり、研究者数も増加している。 HPへ |
 |
大島一正 先生
京都府立大学 生命理工情報学部 理工情報学科 【複合適応形質の進化】 HPへ |
 |
川田健文 先生
東邦大学 理学部 生物学科 機能生物学部門/理学研究科 生物学専攻 【転写因子STATによる細胞分化】細胞性粘菌の転写因子による細胞分化の研究で多くの論文を出している。 HPへ |
 |
赤沼哲史 先生
早稲田大学 人間科学部 人間環境科学科/人間科学研究科 人間科学専攻 【生命の初期進化】 HPへ |
 |
深津武馬 先生
産業技術総合研究所 【多様な昆虫の細胞内共生】いろんな種類の昆虫に細胞内共生している微生物の機能を解明している。その多様な機能には驚くばかり。生物の進化に細胞内共生がいかに大事か、高校生にも感じさせてくれる。 HPへ |
 |
藤田敏彦 先生
東京大学 理学系研究科 生物科学専攻/国立科学博物館 【棘皮動物の分類および生態学的研究】棘皮動物、特にヒトデ、クモヒトデ類の分類及び生態学的研究を行っている。研究拠点は国立科学博物館で、様々な生物と触れ合える環境である。また、深海における棘皮動物の生態探索も、精力的に行っている。 HPへ |
おすすめ本
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。
海外で学ぶなら
Duke University/デューク大学(米)HPへ生物学部 HPへ【生物の進化多様性に関する研究】 生物進化を様々な観点から考えようという学部で解析・思考・実証することを目指している。研究の独自性もさることながら、研究分野を越えたディスカッションの場が大いに提供されている学部である。学生の素朴な関心を世界的な研究に発展させてくれる類まれな大学である。 |
Indiana University Bloomington/インディアナ大学ブルーミントン校(米)HPへDepartment of Biology HPへ【各種ゾウリムシのゲノム解読とその細胞内共生細菌のゲノム解読】 ゲノム情報をつかって、ゾウリムシ属の種の進化を研究している。 |
North Dakota State University/ノースダコタ州立大学(米)HPへ生物科学学部 HPへ【昆虫の進化発生生物学】 昆虫を用いた形態的特徴の進化発生学的研究を行っている。また、それらをもたらす遺伝子ネットワークとの関係からも、昆虫の進化について探究している。 |
McGill University/マギル大学(カナダ)HPへ理学部 HPへ【進化発生生物学】 アリを用いて、カーストをもたらす遺伝子の探究や、種分化の道筋を探究している。各国からの留学生も多く受け入れている。 |
Università di Pisa/ピサ大学(伊)HPへDepartment of Biology HPへ【繊毛虫の細胞内共生生物の多様性】 ゲノム情報をつかって、各種繊毛虫の細胞内に共生する新規細胞内共生細菌の機能と起源を調べている。 |