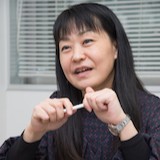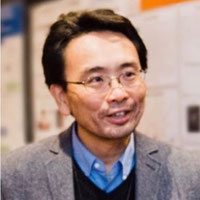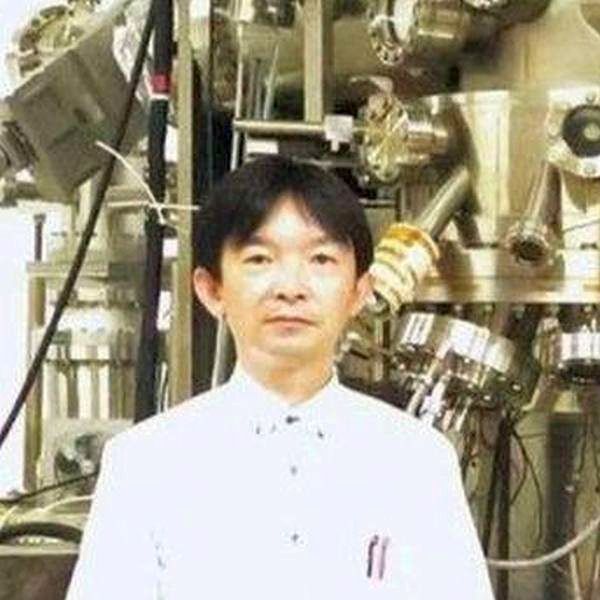学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
山梨大学工学部 工学科HPへ【材料科学】 クリスタル科学研究センターとの連携により、材料科学の専門的な教育を受けることができる。圧電材料に強い。 |
東京理科大学先進工学部 マテリアル創成工学科HPへ【光触媒】 藤嶋昭栄誉教授は光触媒の世界的権威である。 |
明治大学理工学部 応用化学科HPへ【生体材料】 相澤守先生は生体材料の第一人者である。 |
早稲田大学先進理工学部 応用化学科HPへ【新しい多孔体】 多孔体に関して世界的な第一人者である黒田一幸先生の研究室を、現在は、下嶋 敦先生が継ぎ研究に取り組んでいる。 |
豊田工業大学工学部 先端工学基礎学科HPへ【工学全般】 教員に対する学生数が少ないだけではなく、ユニークな研究が多数行われている。 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
忠永清治 先生
北海道大学 工学部 応用理工系学科 応用化学コース/総合化学院 総合化学専攻 【無機材料の合成】無機機能性材料の分野で基礎科学から応用まで幅広く研究。 HPへ |
 |
矢口裕之 先生
埼玉大学 工学部 電気電子物理工学科/理工学研究科 数理電子情報専攻 【電子・電気材料工学】光デバイスやパワーデバイス応用を目指した半導体材料に関するハイレベルな研究を行う。 HPへ |
 |
中島章 先生
東京科学大学 物質理工学院 材料系 【環境材料】光触媒系環境材料の第一人者。 HPへ |
 |
宇佐美徳隆 先生
名古屋大学 工学部 マテリアル工学科/工学研究科 物質プロセス工学専攻 【材料プロセス創成工学】エネルギー問題解決のカギとなる太陽電池の高効率化を目指したレベルの高い研究を行っている。 HPへ |
 |
徳留靖明 先生
大阪公立大学 工学部 マテリアル工学科/工学研究科 物質化学生命系専攻 【ナノ水酸化物】陰イオンとして水酸化物イオン (OH-) を持つ水酸化物ナノクラスターを開発し、国際的に評価されている若手研究者。この新規材料は、バイオセンシング材料、触媒、光触媒材料として期待されている。 HPへ |
 |
芦田淳 先生
大阪公立大学 国際基幹教育機構 【光エレクトロニクス材料、半導体工学、結晶成長】より環境負荷の小さい太陽電池として、酸化亜鉛と酸化銅と接合させたヘテロ接合太陽電池の開発を行う。製造過程でも環境に出てはいけない物質や危険物は使用せず、非常に小さいエネルギーで製造が可能である。 HPへ |
 |
澤野憲太郎 先生
東京都市大学 理工学部 電気電子通信工学科/総合理工学研究科 電気・化学専攻/総合研究所 【ナノエレクトロニクス】半導体材料のシリコンとゲルマニウムを組み合わせた基板を大面積化する技術を開発、低消費電力化に成功した。所属する東京都市大学総合研究所にはクリーンルームや大型研究設備が完備されており、ハイレベルな研究が行われている。 HPへ |
 |
相澤守 先生
明治大学 理工学部 応用化学科/理工学研究科 応用化学専攻 【生体材料】生体材料の第一人者である。 HPへ |
 |
幸塚広光 先生
関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 【ゾル-ゲル薄膜】化学的な手法でゾルをゲル化するゾル-ゲル法によってセラミック薄膜作製し、新しい物性、機能を創出するための基礎的な研究に取り組む。地に足のついたテーマで地道に成果を上げている。 HPへ |
おすすめ本
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。
海外で学ぶなら
University of New Mexico/ニューメキシコ大学(米)HPへSchool of Engineering HPへ【Material Science、Electronic Devices】 日本では一般には有名ではないが、周辺には国立研究機関やテクノロジー志向の強い民間企業が集積しており、それらとの協力の下で活発な研究が行われている。 |
Technische Universität Graz/グラーツ工科大学(オーストリア)HPへInstitut für Physikalische und Theoretische Chemie HPへ【材料化学】 優秀な研究者が複数名在籍している。 |
Universidad de Buenos Aires/ブエノスアイレス大学(アルゼンチン)HPへ【材料化学】 優秀な若手研究者を集めて重点的に資金が注入されている。 |
Universidad Nacional de San Martín/サンマルティン大学(アルゼンチン)HPへINS(Nanosystems Institute) HPへ【材料化学】 優秀な若手研究者を集めて重点的に資金が注入されている。 |