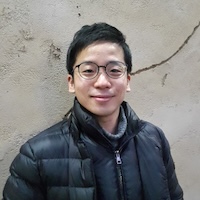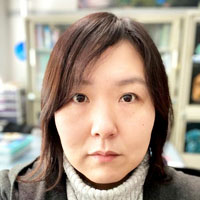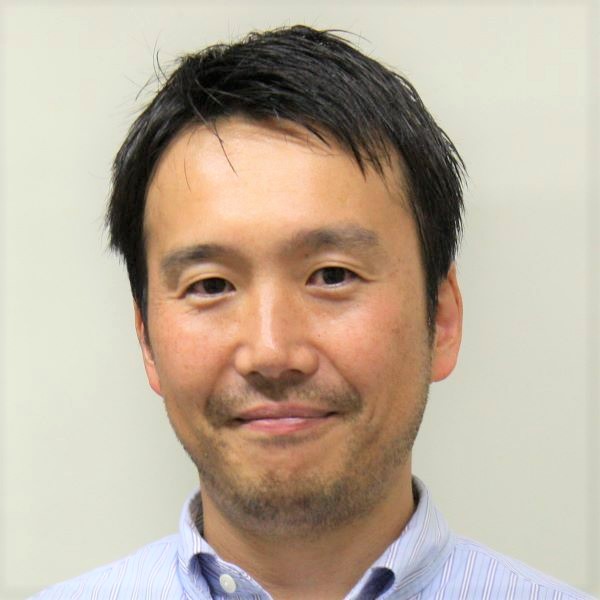学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
秋田大学国際資源学部 国際資源学科 資源地球科学コースHPへ国際資源学部では、文理問わず資源学に特化して、グローバルな研究を行っている。 |
東京科学大学理学院 地球惑星科学系HPへ【地球深部科学】 地球核の研究、地球の形成進化の研究を行っている。 |
島根大学総合理工学部 地球科学科HPへ地質学から工学分野にわたり幅広い教育・研究を実施しており、複合的な自然災害の要因を学ぶことができる。 |
日本大学文理学部 地球科学科HPへ総合的な地球科学の研究・教育を実施しており、学習・教育プログラムがJABEEに認定されている。 |
福岡大学理学部 地球圏科学科HPへ【地球科学分野】 野外調査をもとに、地球表層の古環境変化や地史的な変動過程に関する研究を行っている。 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
大藤弘明 先生
東北大学 理学部 地圏環境科学科/理学研究科 地学専攻 【高圧地球、物質科学】電子顕微鏡を用いた高圧鉱物や微細組織の解析。電顕観察技術を活かして、天然試料、光学系材料の広範囲を守備範囲としている。 HPへ |
 |
鈴木昭夫 先生
東北大学 理学部 地球惑星物質科学科/理学研究科 地学専攻 【地球深部への水の輸送に関する実験的研究】超高圧高温実験で、地表から地球中心核に至る極限環境をの構造進化の過程を解明。 HPへ |
 |
興野純 先生
筑波大学 生命環境学群 地球学類 地球進化学主専攻/理工情報生命学術院 生命地球科学研究群 【鉱物合成、結晶構造解析】天然、合成鉱物の研究だけではなく、理論計算からもそれを実証していく。 HPへ |
 |
芳野極 先生
岡山大学 環境生命自然科学研究科/惑星物質研究所 【地球深部への水の輸送に関する実験的研究】高圧発生装置を用い地球深部を構成する物質の物性を決定づける実験的研究を行っている。 HPへ |
 |
土屋旬 先生
愛媛大学 理学部 理学科 地学コース/理工学研究科 数理物質科学専攻/地球深部ダイナミクス研究センター 【高圧鉱物理論物性学】地球の基本構成単位である鉱物について、組成とその結晶構造や、地震、波速度などの物理的性質を明らかにする。コンピュータシミュレーションを用い、地球の構造や進化の過程を知ることを目指す。 HPへ |
 |
瀬戸雄介 先生
大阪公立大学 理学部 地球学科/理学研究科 地球学専攻 【隕石、地球深部物質】隕石組織について再現実験を行っている点がユニーク。また地球深部物質も研究対象としている。さらにソフトウェア開発にも積極的に取り組んでいる。 HPへ |
おすすめ本
史上最強カラー図解 プロが教える鉱物・宝石のすべてがわかる本
下林典正、石橋隆:監修
まず美しい鉱物の写真が目に飛び込んでくる。自然界でこのようにカラフルで美しい結晶がみられることに純粋に驚かされる。この本は、それぞれの鉱物の解説も充実しており、かつ鉱物を理解するために必要な基礎知識をわかりやすく、しっかり説明している。また産業界、学術界でプロフェッショナルとして鉱物と関わる人たちのコラムは必読。鉱床探査、海底資源、都市鉱山、宝石の鑑別など興味深いテーマばかりだ。岩石・鉱物・鉱床学という学問分野そのものの紹介と言える。専門家だけではなく、鉱物に興味がある初学者に適した書籍でもある。 (ナツメ社)
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。