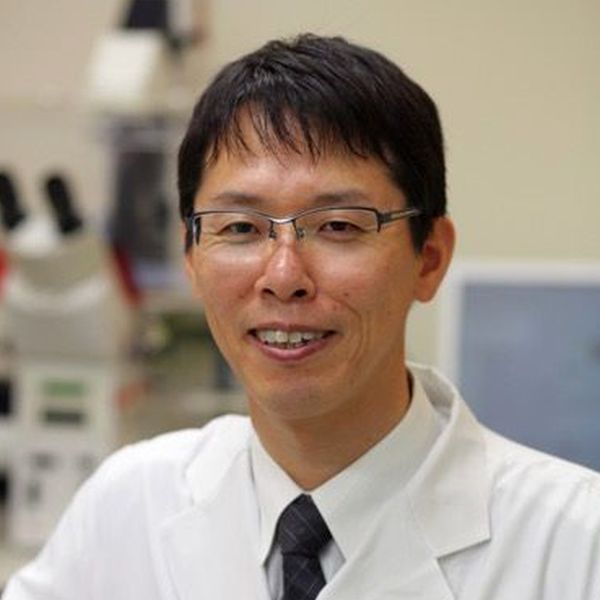学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
岡山県立大学保健福祉学部 栄養学科HPへ【食品学】 食品機能に関する研究で評価が高い。 |
県立広島大学地域創生学部 地域創生学科 健康科学コースHPへ【臨床栄養学】 高齢者の食事の研究が注目されている。 |
女子栄養大学栄養学部 実践栄養学科HPへ【栄養学全般】 栄養学教育に歴史がある大学で、きめ細かい教育が行われている。 |
明治大学農学部 農芸化学科HPへ【農芸化学】 食品・微生物・栄養・環境について広く学び深く研究する。 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
新井英一 先生
静岡県立大学 食品栄養科学部 栄養生命科学科/薬食生命科学総合学府 食品栄養科学専攻 【臨床栄養学】慢性腎臓病患者における高リン血症の栄養管理について研究している。特に、食事パターンや調理によるリン摂取量の変動に詳しい。 HPへ |
 |
岩崎有作 先生
京都府立大学 生命環境学部 農学生命科学科 生物機能科学コース/生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 【栄養生理学】食欲や食行動を分子神経学的に解析している。 特に、食欲と肥満やメタボリックシンドロームとの関連についての研究で成果を挙げている。 HPへ |
 |
伊藤美紀子 先生
兵庫県立大学 環境人間学部 環境人間学科 食環境栄養課程/環境人間学研究科 環境人間学専攻 【臨床栄養学】慢性腎臓病患者のリン代謝異常に関する研究を行っており、食品添加物に関する研究や患者の栄養評価法に詳しい。 HPへ |
 |
黒尾誠 先生
自治医科大学 医学研究科 人間生物学系専攻/分子病態治療研究センター 【老化学】老化関連遺伝子であるKlothoの発見者である。Klothoの異常による早期老化様の症状の原因が高リン血症によるものであることを明らかにし、その分子メカニズムの解明に取り組んでいる。 HPへ |
 |
宮本賢一 先生
龍谷大学 農学部 食品栄養学科/農学研究科 食農科学専攻 【分子栄養学】体内でのリンの吸収や排泄に関わるリン酸トランスポーター研究分野において、世界の第一人者である。栄養素がどのように吸収され利用されるかを、トランスポーターを通じて解明しようと取り組んでいる。 HPへ |
おすすめ本
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。