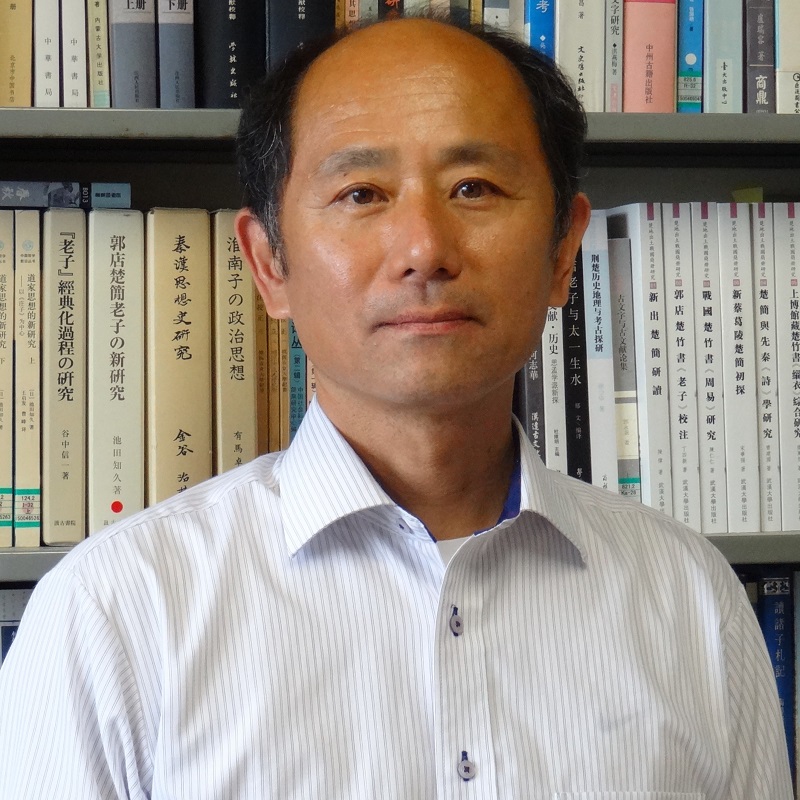学べる大学は?
研究をリードする大学
 |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
注目の大学
北海道大学文学部 人文科学科 言語・文学コースHPへ中国哲学、中国語学、中国文学の三つがまとまっている「中国文化論教室」で、中国学を幅広く学ぶことができる。 |
二松學舍大学文学部 中国文学科HPへ漢学者の三島中洲によって創建された大学である。その建学の精神はいまも生きていて、スタッフも重厚である。 |
活躍する研究者
こんな研究で世界を変える!〜最新研究を読もう
注目の研究者
 |
近藤浩之 先生
北海道大学 文学部 人文科学科 言語・文学コース/文学院 人文学専攻 【易学、出土文字資料】古代中国の思想『易』研究の第一人者。日本では占いでおなじみだが、中国では宇宙観や思想、学問すべての原理として最上位に置かれる経典として知られる。易研究のほかに日本の漢学もよく研究している。 HPへ |
 |
井川義次 先生
筑波大学 人文・文化学群 比較文化学類 思想文化領域 現代思想コース/人文社会ビジネス科学学術院 人文社会科学研究群 【欧米への宋学の影響】欧米の近代哲学に与えた中国思想の影響を明らかにする。 HPへ |
 |
小島毅 先生
東京大学 文学部 人文学科 中国思想文化学専修課程/人文社会系研究科 アジア文化研究専攻 【宋学、宋代以後の儒教、日本思想】中国思想史で、中でも宋から清にいたる時期の儒教研究の第一人者。朱子学の形成と展開の過程を哲学史に限定するのではなく、当時の政治文化の文脈から再検討してきた。中国学の立場から日本思想にも発言している。 HPへ |
 |
中島隆博 先生
東京大学 教養学部 教養学科 超域文化科学分科 現代思想コース/総合文化研究科 超域文化科学専攻/東洋文化研究所 【老荘思想・新儒学】欧米の哲学と中国の思想を対比。 HPへ |
 |
池田恭哉 先生
京都大学 文学部 人文学科 中国哲学史専修/文学研究科 文献文化学専攻 【中国中世思想史】哲学と文学の境界領域の研究を開拓している。今後が期待される若手のホープ。 HPへ |
 |
宇佐美文理 先生
京都大学 文学部 人文学科 中国哲学史専修/文学研究科 文献文化学専攻 【中国芸術思想】中国の芸術に関する思想を中心に研究している。視点がユニーク。 HPへ |
 |
名和敏光 先生
山梨県立大学 国際政策学部 国際コミュニケーション学科 【中国出土文字資料】国内より国外の知名度が高い、出土文字資料研究の第一人者。 HPへ |
おすすめ本
『論語』と孔子の生涯
影山輝國
中国から伝えられた書籍(漢文で書かれているので、これを漢籍と呼びます)の中で、古来、日本人が最も愛読したのは『論語』です。『論語』は孔子とその門弟たちとの対話を集成したもので、これを読めば「儒教」という思想が何となくわかります。しかし『論語』は断片的な対話から成り立っているため、初心者にはちょっと難解です。そこで入門書が必要となるのですが、これまで書かれた入門書はおしなべて小難しい内容で、とくに中学生や高校生からは敬遠され気味でした。
ところが、ここに紹介する影山さんの著書はその先入観を吹き飛ばす画期的な入門書です。記述がわかりやすく、しかも面白い。その面白さはどこから来ているかというと、中国では滅んだが日本にのみ現存する『論語義疏』という注釈書を中心に据えて筆を進めているからでしょう。『論語』の面白さは解釈の多様性にあり、本書はそのことを非常にうまく説明しており、まさに名著です。
(中公叢書)
情報系 化学技術全般
暗号解読 ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン・シン
最先端領域に宿る天才たちの壮絶なドラマ。歴史の背後に秘められた、暗号作成者と解読者の攻防―加速する情報戦争の勝者はいったい誰か?『フェルマーの最終定理』に続く世界的ベストセラー、待望の完全翻訳版。