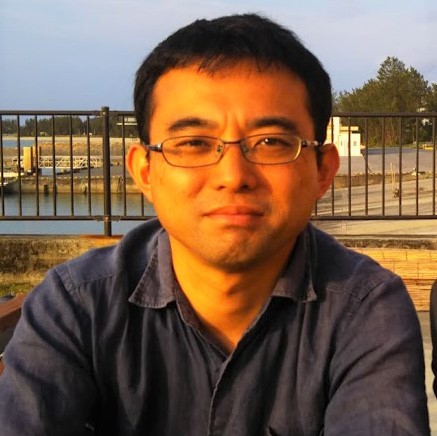世界ではもちろん、実は日本国内でも、これまで学術的に存在が認められていなかった新種が毎年発見されつづけています。「生物多様性・分類」分野の中心の一つは、これまで学術的に知られていなかった生物を報告し、名前をつける新種記載に関する研究です。こうした研究を行うことは、種とは何かという問題に向きあうことでもあります。

種とは、おおざっぱに言うと、他の集団とは生殖的に隔離された独立した集団とされています。しかし、物事は単純ではありません。実際には非常に近縁な生物の種間で、野外でも交雑が起こり、生殖能力がある雑種が生まれることがあります。そのような場合でも、雑種が子孫を残す確率が両方の親種に比べて低いため、親種同士の遺伝的な独自性が維持されることもあります。こうした知見が、「2つの集団は同種か別種か」という判断をするうえで重要な根拠になります。
特に私の研究対象の両生類では、外見上はよく似ているがDNAレベルで調べてみると大きな分化が見られ、一つの種と思われてきたものの中に、実は複数の種が含まれていたという事例が多くあります。現在、日本本土のアカハライモリや、琉球列島の両生類の幾つかの種の地域集団間の分化について調査しています。これまでの調査から、国内のアカハライモリ、琉球列島の両生類の幾つかの種には、遺伝的に非常に大きく分化した集団が含まれ、その違いは別種レベルにまで達していることが明らかになってきました。また、そうした遺伝的に分化した複数の集団が地理的に接する地域で、集団間の生殖的な隔離の実態や、片方の集団の遺伝子がもう一方の別の集団へ浸透しているかどうかなどを詳しく調べています。
野生動物の保全のためにも、正しく種を把握する
近年、野生生物の減少が危惧され、早急な生物の保護・保全対策が必要とされています。そのとき、数の少ない希少な種は保全上注目されることが多いのに対し、広い範囲に分布する生物は、個体数も多く絶滅の可能性が低いと一般的には捉えられます。しかし、もし、この中に幾つかの種や大きく分化した遺伝集団が含まれていると話は変わります。正しく保全するために、正しく生物の多様性の実態を把握する必要があります。こうした保全や保護の基礎となる情報を提供するのも、この分野の重要な役割だと考えています。

大学生との干潟での生物観察の様子
一般的な傾向は?
- ●主な業種は→教育関係
- ●主な職種は→理科に強い小学校の教員、中学校の理科教員、高等学校の理科(生物)の教員
- ●業務の特徴は→児童生徒の将来を担うとてもやりがいのある仕事だと思います
分野はどう活かされる?
大学で学んだ生物の知識を小中高の教育に取り入れて、児童生徒の自然科学に関する関心を高めてくれていると期待しています。
どんな分野でも物事の真理を追求し努力し続けることは、その分野の能力や知識の向上だけでなく、自分自身の成長や、様々な状況下での確固たる自信にも繋がると思います。また、自分の専門分野を極めようと努力することは、他の分野の価値を理解することにも繋がるのではないかと思います。大学や大学院では、自分の核にしたいと思えるような分野を見つけて、まずはそれを極めることを目指すのもよいと思います。
琉球大学の教育学部理科教育専修には、物理、化学、生物学、地学、理科教育学の各分野の研究者が在籍し、これらの分野について知識を深め、研究することが出来ます。理学部の海洋自然科学科生物系には、生態学、進化学を含む、多くの分野の多くの研究者が在籍し、亜熱帯島嶼の環境で、様々な研究ができます。農学部の昆虫学の分野では、亜熱帯島嶼の環境で、昆虫の生態、進化に関する様々な研究を行っています。

大学生との野外実習の一コマ