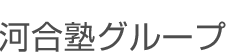第3回 卒論は村上春樹。しかし、大学院では正岡子規へ
たった十七字で世界が終わるのがとにかく新鮮
青木先生:俳句研究をしっかりやりたいと感じたのは大学院に入ってからです。学部生の頃は小説ばかりで、卒業論文も村上春樹でした。私の評論集『その眼、俳人につき 正岡子規、高浜虚子から平成まで』(邑書林)の冒頭に村上春樹『アフターダーク』を引用したのも、昔からよく読んでいたためです。同時に俳句も好きで、小説と同時並行で読んでいました。
俳句でいえば、中学校の時に江戸時代の俳諧集『猿蓑』を読んで、素人ながら芭蕉や凡兆はすごいなとしきりに感心していました。大学に入り、与謝蕪村や平安期の古今集や新古今集、また江戸時代の小説といった古典も好きで、近現代俳句も昭和期の新興俳句といった前衛的な作品や、高浜虚子のように王道の俳句も自己流で乱読していましたね。
大学が京都市内だったので、まだその頃には市内に古本屋さんが結構ありましたし、季節ごとの古本市も盛んでした。そういうところで俳句関連の文庫シリーズが安く売られていたので、まとめて買って読んでいたんです。俳句に惹かれたのは、とにかく短いということ。あれほど短いのに作品として完結したことになっているのがすごいな、と。当時は小説を読むことが多かったので、たった十七字で世界が終わるのがとにかく新鮮でした。

佐藤さん:俳句って、実作から興味を持つ人も多いと思います。私自身、俳句を作るところから入りました。青木先生は俳句を読んでいて、作りたい気分にならなかったですか。
青木先生:なぜか「作る」方には気持ちが動かなかったです。朝起きた時に傑作が浮かんだらステキだなあとは思いましたけど、そういう奇跡があるはずもなく、作品を「読む」方が面白いと感じていました。
本当は高浜虚子研究がしたかったが、まずは子規から
佐藤さん:それで大学院に入って正岡子規を、と。なぜ正岡子規を研究しようと思ったんですか。
青木先生:本当は高浜虚子と『ホトトギス』(虚子が率いた俳句結社雑誌)を研究したかったんですよ。近代俳句を自己流で読む中で、虚子の句が一番変だなと感じたんです。加えて、虚子門下でいば中村草田男や川端茅舎、原石鼎等々、虚子の「ホトトギス」で句作をした俳人たちの異常なテンションの高さが気になって、文学研究者のアプローチで彼らの句を解釈したいと思ったんですが、手に負えない感覚を抱きました。作品があまりにすごくて、今の自分の力量では歯が立たない気がしたんです。
これは方向を変えなければいけないというので、そもそも高浜虚子のような俳人を誕生させた明治時代の正岡子規から始めようと思いました。近代俳句の生みの親から研究すれば、虚子や草田男の秘密が探れるのではないか、と感じたわけです。
研究計画としては、正岡子規は五年ほどで終える予定でした。それから高浜虚子に進み、時代も明治から大正、昭和時代に移るつもりだったのですが、子規の研究に相当時間がかかり、結局マスター(修士)、ドクターコース(博士)、そして博士論文も全て子規研究に費やすことになりました。見込みが甘すぎましたね(笑)。
佐藤さん:『その眼、俳人につき』の中の「愛と執着、または起風機—碧梧桐・虚子から見た子規−−」に、子規の人柄が感じられて面白かったです。子規っていうのはこんな冷徹だった、という。
青木先生:今では子規は英雄とされていますが、人としてはかなりアクの強い性格だったと感じます。同年輩の友達よりも後輩を従えるタイプで、例えば同年配でも夏目漱石は常識的で配慮もできる人で、相手を立てることができた性格なので、子規と付き合えた気がします。
そもそも、子規は東京帝国大学という日本最高の出世コースの一つを退学しましたからね。一族や親戚からすれば、あれだけお金をかけて東京へやったのに、文学なぞにハマって一体何を考えているんだ!と。松山の血縁者からはそうとう怒られたと思うんですよね。子規は学生時代に結核になってしまったという理由はありますが、明治時代に文学に熱中して学業を顧みないなどというのは、「あいつには関わるな」と周りから冷ややかに見られていた側面も強かったように感じます。ただ、松山の後輩にあたる河東碧梧桐や高浜虚子はそういう不良先輩(?)の子規に強烈に憧れを抱いていたので、子規は良かれ悪しかれカリスマのようなオーラを持っていた人だったように感じます。