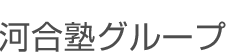ゾンビ(原題:Dawn of the Dead)
ジョージ・A・ロメロ:監督, 1978年
ゾンビ映画の金字塔で、無数のフォロワーを生んだ作品。何といっても、ゾンビの群れがうろつく舞台をショッピングモールに設定したのがすばらしい。
モールに集まってくるゾンビについて、つぎのような会話が交わされる。「奴らは何をしているの? なんでここにやってきたの?」「本能のようなものさ。記憶だよ。彼らがいつもやっていたことのね。彼らの生活で、ここは大事な場所だったんだ」。人びとはゾンビ化したあとでも、生前の記憶が残存しており、モールに何となくやって来てしまうのだ。これは逆にいえば、ぼんやりとモールをうろつく私たち消費者=現代人は、そもそもゾンビのようなものだ、ということでもある。ゾンビ映画が人気を継続しているのは、私たちがゾンビに、自分たちの似姿を認めているからでもあるだろう。
ゾンビとしての私たちと、快適な消費空間としてのモール(あるいは現代的な都市環境の全体)。この組み合わせに、何かぞわぞわとするものを感じるようなら、それが、都市のあり方を批評的に考えるうえでの第一歩となる。
ファミレス的「でない」ものに、街の「個性的」を求めるのは
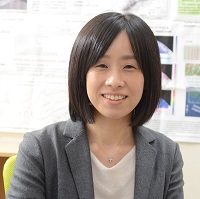
町中華は「ちょっと個性的」
「昭和」を思わせるレトロな喫茶店や「町中華」などが、最近では若者世代に人気が出てきています。それらの喫茶店や「町中華」は、2000年頃までは、ありふれていて、むしろ少しダサいと思われていたお店です。
それらが「ちょっと個性的」なお店として好まれるようになった(「町中華」という呼び方自体、2010年代以降に出てきた呼び方です)理由は、何なのだろう? それは、私たちが街に感じる個性/無個性の感覚とどうつながっているのだろう? ――そんなことを考えています。
どこにでもある買い物環境と個性/無個性
以前から気になっているのは、コンビニやファミレス、ショッピングモールなど、どこにでもある買い物環境と、私たちが街に感じる個性/無個性の感覚との関係です。
たとえば情報番組の街ロケでの「あるある」として、出演者が、商店街のお肉屋さんでコロッケをほおばるシーンが出てきます。こうした場面が「あるある」になったのは、コンビニやファミレスのような買い物環境がたくさん増えた結果、コンビニ的「でない」もの、ファミレス的「でない」ものを、少し「個性的」なものとして、私たちが求めるようになったからではないか、と考えています。
無個性的なサイゼリヤにも愛着はもてる
その一方、私たちは、一見すると無個性的なコンビニやファミレスにも、それなりの愛着をもつことができます。たとえば仲間たちと、いつも部活終わりにサイゼリヤでおしゃべりをしていたとすれば、「あの、かけがえのない思い出のあるサイゼリヤ」となるのではないでしょうか。そしてまた「商店街のお肉屋さん」自体も「個性的」であると同時に、ある種のワンパターンさをそなえているように思えます。
私たちが街に感じる個性/無個性の感覚は、つねに動いており、個性的だったものがありふれたものになったり、ダサいと思われていたものがおしゃれになるなど、お互いに入れ替わったりします。この動きを読み解くなかで、街を「おもしろく」したり「つまらなく」したりする条件とは何かという問題を、考えています。


吾輩は猫である
夏目漱石(新潮文庫)
あまりに有名すぎるので、実際に読んでみたという人はあまりおらず、「猫が主人公の風刺がきいたユーモア小説ですよね」くらいの教科書的な認識しかない方も多いかと思いますが、具体的なストーリーがどうこうというよりも、「文体」というものを体験できる読み物として、お薦めします。圧倒的教養をベースに「言葉」で遊んでみせる漱石の文体は、リズムとグルーヴがすさまじく、「うわっ…」と思わせてくれます。
私自身は五回くらい読んで、お気に入りのフレーズが脳にしみついています。(読むというより、アトラクションとして楽しむ、という感じの方が近いでしょうか。)「猫などはそこへ行くと単純なものだ。食いたければ食い、寝たければ寝る、怒るときは一生懸命に怒り、泣くときは絶体絶命に泣く」というところの、「絶体絶命に泣く」というフレーズとか、「「こないだうちは利いたのだよ、この頃は利かないのだよ」と対句のような返事をする」という箇所の「対句のような返事」というフレーズが、お気に入りです。(具体的な箇所は、「青空文庫」で無料で読めるテクスト内で検索をかければすぐに出てきますので、チェックしてみてください。)