生き物のようなふるまいを実験室で生み出す

生き物は自分で構造をつくったり動いたりできる
私たちの体のような「生きているシステム(生体システム)」を見てみると、エネルギーが常に流れ続ける中(=非平衡の状態)で、外からエネルギーを取り入れることで、自分の形や構造を変えたり(動的自己組織化)、周りの力に逆らって動いたり(能動的運動)しています。
たとえば、私たちは食べ物からエネルギーをもらうことで、時間とともに成長したり、坂道を登ったりすることができます。一方で、人間がつくってきた人工的なシステム(工業や産業のしくみ)では、製品は設計図に従って部品を組み立てることでつくられています。また、化学の世界でも、物質が動くしくみは多くの場合、周りの環境に影響された「受け身の動き」に頼っています。
「動的自己組織化」や「能動的運動」は複雑で謎が多い
このように比べると、生き物のしくみはとてもスマートで、自分で構造をつくったり動いたりできる点が大きな特徴です。ですが、生き物が当たり前のように行っている「動的自己組織化」や「能動的運動」のしくみは実はとても複雑で、まだ詳しくわかっていません。そのため、生き物のような性質を持つ人工的なシステムをつくる技術も、まだほとんど実現していません。
私たちの研究室では、生き物のようなふるまいを工学に応用することを目指し、その第一歩として、できるだけシンプルな化学実験を通して「動的自己組織化」や「能動的運動」といった非平衡現象を示す新しいシステムをつくり出し、それらの現象がなぜ起こるのかを研究しています。
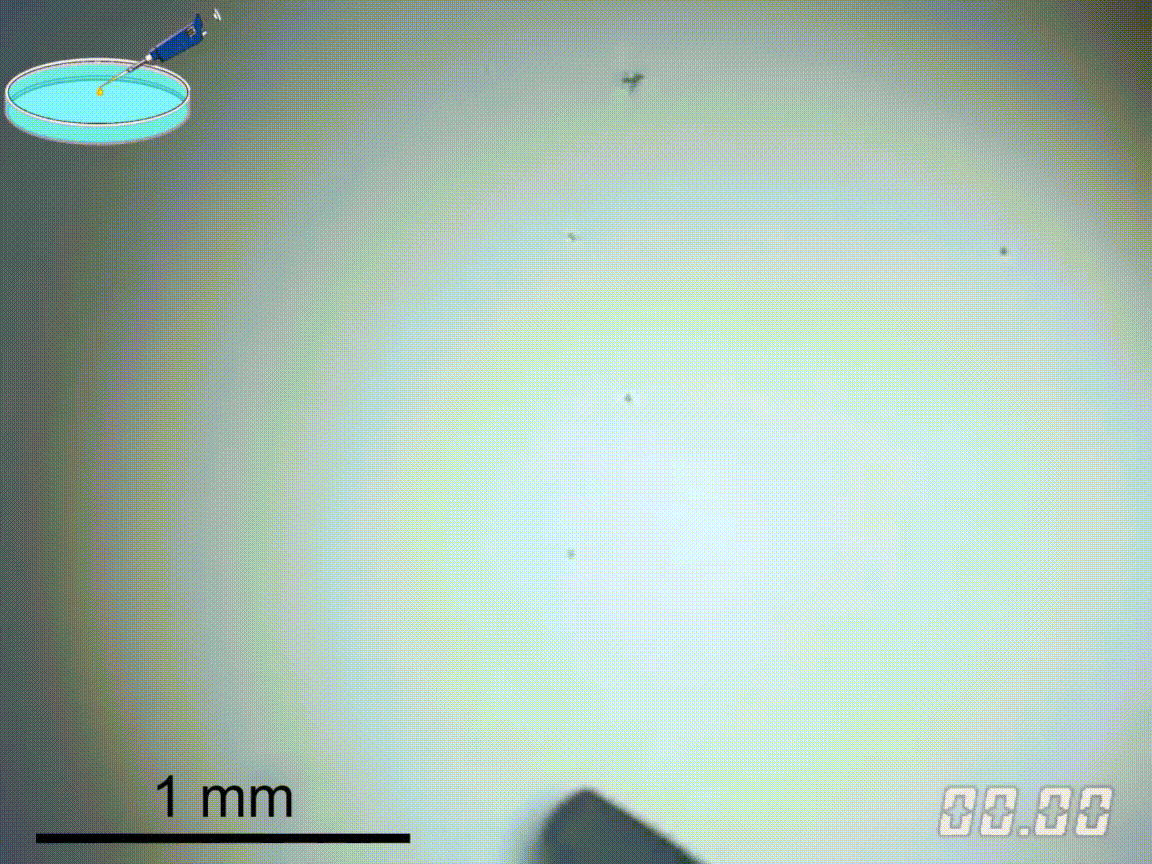

上:水面上でのフッ素油(Perfluorooctyl bromide)の液滴のパターン変化(動的自己組織化の例)
下:水溶液中で反応物質によって異なる方向に回転運動を行う白金触媒粒子(能動的運動の例)
私の専門分野は化学工学です。学生時代は、反応の場をいかに制御して目的のサイズの粒子をつくるか、またそのしくみを解明するといった、まさに化学工学的な研究をしていました。
その後、博士号を取得して研究者になった後、縁あって同志社大学に赴任しました。そこで同じ研究室を率いる塩井章久教授と出会い、大きな刺激を受けました。先生は当時は化学工学ではまだ馴染みの薄かった非平衡現象に早くから注目し、長年にわたり探究を続けてこられた稀有な化学工学者です。その影響を受け、私自身も、時間・空間的に変化していく非平衡現象の奥深さと面白さに強く惹かれるようになりました。
「単純なマクロ操作によって発現する動的自己組織化パターンの制御に関する研究」
◆同志社大学 分子化学工学研究室
→研究室HPはこちら
本研究室で見つけた現象は、実際に動画で見るとよりわかりやすく、面白さが伝わると思います。ここでは紹介しきれなかった実験や現象もたくさんありますので、ぜひこちらのQRコードや下記URLから、分子化学工学研究室の研究を見てみてください。
◆https://www1.doshisha.ac.jp/~molcheng/research.html

SF(空想科学:Science Fiction)作品全般をお勧めします。漫画でも映画でも小説でもなんでもいいです。SF作品には、ワクワクする未来のアイデアがたくさん出てきます。
ドラえもんの歌にある 「あんなこといいな、できたらいいな」 みたいに、今はまだ実現できていないけど、もしできたらすごい! という道具や魔法がいっぱい登場しますよね。でも、それってただの夢じゃなくて、研究のヒントの宝庫かもしれません。
| Q1.一番聴いている音楽アーティストは? Superflyです。同郷ということもあって家族で応援しています。元気が欲しいときに背中を押してくれる存在です。 |
|
| Q2.感動した/印象に残っている映画は? 一番印象深い作品は「ハリーポッターシリーズ」です。映画館では終始ワクワクドキドキしていましたが、映画の内容によるものだったのか一緒に誰と見たかによるものだったのか要因は未だ不明です。 |
|
| Q3.学生時代に/最近、熱中したゲームは? ポケモン、ドラクエシリーズです。学生時代、時間を忘れてやりこみました。 |
|
| Q4.大学時代のアルバイトでユニークだったものは? 個人経営の本屋さんでアルバイトしていました。当時としては珍しく、近隣の飲食店へ週刊誌や月刊誌を配達する業務もあり、地域のみなさんとのつながりを感じられるアルバイトでした。 |




