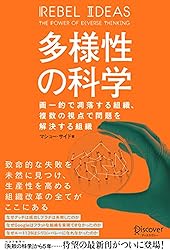地域住民が無理なく楽しく続けられる防災学習

なぜ人は自然災害に十分な準備をしないのか
皆さんは地域で行われる防災訓練に参加したことがありますか。学校での避難訓練だけだったり、子どもの頃に親と参加したきりだったりする人も多いでしょう。中には「やってみたけど、本当に役に立つのかな?」と感じたことがある人もいるかもしれません。
日本では毎年のように地震や台風が起き、ニュースでは「地域で協力して乗り越えた」事例が紹介されます。でも、次にいつどこで起こるかわからないのに、なぜ多くの人は十分な準備をしないのでしょうか。私はこの「わかっているのに備えない」という人間の不思議に挑んでいます。
地域のニーズに応じた防災訓練や防災イベント
人々が災害に備えるための研究にはさまざまな分野があり、心理学は人の心を、社会学は人のつながりを扱い、訓練やイベントの内容を検討する研究もあります。私はこれらを活用し、いかに無理なく災害対策を進められるかを探究しています。ここでいう「無理なく」とは、手軽に準備できたり、楽しみながら実践できる防災を指します。
私の研究は、地域の状況に応じて住民自身が最適な防災訓練やイベントを選べる仕組みづくりです。例えば、参加者を増やしたい場合は、対象者に合わせて楽しさを取り入れつつ防災意識を高める企画を行い、少人数で特定の課題に取り組む場合は、その課題克服に特化した集中型訓練を実施します。
このように地域のニーズに応じて選べるシステムを整えることで、住民にも外部の支援者にも無理なく続けられる防災を目指しています。
「みんな」が自然に関われるように変えていく
防災と聞くと深刻であまり関わりがないなと思うかもしれませんが、時には楽しみながら行い、時には真剣に地域の安全に貢献していることを実感できれば、参加・協力したいと思う住民も多くなるかもしれません。防災を「特別な人」ではなく「みんな」が自然に関われることに変えていくこと、それが私の研究の目指す社会です。

実は私は高校から大学院修士課程まで、発展途上国への国際協力に関心を持ってきました。そのため、タイのNGOやフィリピンの政府機関でインターンシップを経験し、卒業論文でもそれぞれの国が抱える課題に取り組みました。
ところが、一度大きな災害が起きると、それまでの努力が水の泡になるだけでなく、大切な人の命さえ失われてしまうことを知り、平時の課題解決だけでは十分ではないと痛感しました。防災はすべての国や分野に関わるテーマであり、持続可能な開発の核となるものだと考えるようになり、現在に至っています。

「防災学習の場と人々の関係性の現実・仮想環境に着目した防災学習手法に関する研究」
◆主な業種
(1) 官庁、自治体、公的法人、国際機関等
◆主な職種
(1) 営業、営業企画、事業統括
◆学んだことはどう生きる?
学部は文系に属するため、学生は自身の興味に応じて、民間企業、公務員、大学院進学など、さまざまな進路を選択しています。
政策科学部は、さまざまな学問を取り入れて政策を学ぶ学部です。特徴的なのは、どんな政策が良いのかを考えるだけでなく、政策がどのように決まるのか・決めるのか、その仕組みまで研究の対象にしている点です。
さらに、文系と理系の先生がそろい、日本語で学ぶ専攻と英語で学ぶ専攻もあるため、多様な教員や学生が互いに刺激し合っています。現場での体験を重視したカリキュラムを通して、人によって問題の見え方が違うという社会の難しさを学びつつ、問題解決をめざして幅広いテーマに取り組むことができます。

・どうすれば備蓄をもっと進められるのか
防災は身近なテーマですが、さまざまな学問を結びつけて考える必要があります。自分や家族、友人を例にして、なぜ準備をしないのか、どんなきっかけがあれば準備するようになるのかを調べてみましょう。その際には、心のあり方や周囲の人の影響、地域の支援体制、地域で行われている防災訓練の内容、さらには防災情報の伝え方に注目してみてください。
NHK高校講座:地理総合
自然環境と防災:第19回 防災にどう向き合う? ~自然災害と防災~
高校講座ですが、内容は難しくありません。動画の前半では、自然災害に向けてどのような対策が行われているのかが説明されています。後半では、地域でどのようにすればよいのかなどについて紹介されています。
動画にもあるように、防災には正解がないことが多く、何をするべきかはみんなで話し合って決めていく必要があります。ここが、どのように決めるのかを研究する、私が所属する政策科学部の醍醐味でもあります。また、この動画では防災ゲームの紹介もされており、どのような防災訓練が実施されているのかを知ることができます。このように簡単ではありますが、現在の防災がどのように進められているのかを知ることで、自分の身の回りの対策や課題について調べたり、考えたりするきっかけになると思います。
[webサイトへ]
| Q1.18才に戻ってもう一度大学に入るならば、学ぶ学問は? 政策科学部 |
|
| Q2.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? 大学教員以外の立場でどのようにして地域防災を促進できるかを色々な人と話して考えること |
|
| Q3.好きな言葉は? 脱完璧主義 |