フェミニスト現象学入門-経験から「普通」を問い直す
稲原美苗、川崎唯史、中澤瞳、宮原優(ナカニシヤ出版)
マジョリティ中心の哲学が無視し続けてきた経験を言語化し、それまで哲学のフィールドに存在していなかった人々(マイノリティ側にいる人々)と一緒に様々な問題について深く考えてみたいー 編者4名のそのような想いからこの本は生まれました。身振り、月経、妊娠、出産といった女性特有のテーマから、人種、障害、男性、トランスジェンダー、カミングアウト、老いなどの経験まで考えてもらえるような入門書です。
この本は、それぞれの当事者たちの経験を記述し、マイノリティ側から私たちが生活している社会の「普通」「当たり前」「規範」を問い直しています。現象学やフェミニズムを初めて知る人にも、手に取って読んでもらいたい一冊です。
対話の中でジェンダーやマイノリティの問題を学ぶ
「普通」って何?「当たり前」って何?

「当たり前」を問うことから見えてくる世界があります。
私自身、マイノリティ当事者(障害者)として生きているので、社会の中の不条理を感じることも多くあります。幼い頃から「当たり前」「普通」という言葉が苦手で、社会の規範に従うことができない自分が好きではありませんでした。
幼稚園や小学校で、「そうするのが当たり前です」「普通にしなさい」などと言われると、クラスの皆と同じようにできなくて、悔しい思いをたくさんしました。その度に「当たり前って何」「普通ってそんなに良いの」って疑問を抱きました。大人になってからでしたが、その答えをくれたのが「哲学」でした。
決めつけや規範が多い
障害者として生まれたことで、自分の言葉で自分を説明することができないことに気が付きました。「障害者」というカテゴリーに入れられることで、私自身の「私」ではない「障害者としての私」が構築されてしまって、「普通ではない」「異常な」身体や声を持って生きている「かわいそうな人間」として生きることを強いられてきました。
小中学校時代にいじめられた経験がありますが、私自身、これまで幸せに生きてきました。しかし、社会の中では、「障害者だから…」「女性だから…」「〇〇だから…」という決めつけや規範が多くあり、自分の言葉で自分を説明することができていないことに気付きました。
問いに答えようとする「過程」を重視する哲学
哲学という学問を学んで、「当たり前」や「普通」を問うことがいかに難しいことなのかがわかりました。「当たり前」や「普通」という前提があることを自覚して、物事を考えてみましょう。哲学とは、先人たちがしてきたように、「当たり前」や「普通」のことに疑問を投げかけることだと思います。哲学は問うことから始まります。問いが出されると、私たちは考えます。
ただし、学校で教えてもらうような、問いに対する答えがある問いを解くのではなく、私たちが生きていく上での答えのない問い(または、答えが簡単に出せない問い)を考えることが必要になります。哲学は、問いを投げかけ、それに答えようとする「過程」を重要視する学問です。すぐに答えが出るような問いではありません。
「私にとって恋愛とは」と「恋愛とは何か」
哲学は大きく二つに分けられると思います。一つ目は、自分自身に問いかけることです。例えば、「私はどのような人生を送りたいのか」「私はどのように働きたいのか」「私にとっての幸福とは何か」などの内省によって、自分のことをより深く探究すること。
もう一つは、他者や社会など、自分自身の外に向けて問うことです。具体例として、「人間は本気で愛し合えるのか」「愛と恋はどのように異なるのか」「現代社会で私たちは自由に語られているのか」「なぜ社会に法律が必要なのか」などを問うことによって、社会のシステムや私たちの思い込みについて考え直すことができます。
つまり、私にとっての「恋愛」「自由」「法律」を定義することだけでなく、「愛とは何か」「自由とは何か」「法律とは何か」という問いを深く探究することにより、常に本質を追い求めようとします。
「どうしていけないのか」徹底的に考える
ここで必要なのは、「なぜそのように考えるのか」という理由を問うことです。理由を問い、それについて語るということが「哲学」だと私は考えます。「正解」を早く出すことを重視するのではなく、「考える過程」を大切にすることに価値があります。
例えば、能力が高い人には生きる価値があり、能力の低い人には生きる価値がないという考え方が優生思想だということは、おそらくご存知だと思います。この思想は人権を侵害してしまう、とても危険な考え方です。
皆さん、優生思想を持ってはいけないと道徳などの人権教育の時間に学ばれたと思います。しかし、「優生思想を持ってはいけない」という一般的な印象によって判断することは哲学ではありません。「どうして優生思想がいけないのか」という理由を徹底的に考えなければ、哲学をすることにはならないのです。つまり、その理由を多角的に考える過程が哲学なのです。
他者の考えを聞くことも大切
私たち人間は、他者と共にコミュニティの中で暮らしています。しかし、「コミュニティ」という決まった本質が存在しているわけではありません。日常生活の中で、私たちは他者とともに様々な活動をし、実際に生活をすることによってでしか「コミュニティ」の存在を感じられないので、その場にいる人々とともに対話するということがとても重要になります。
一人で考えると、考えが偏ってしまい、広がり深まりにくくなります。自分で考えたことを他の誰かに伝えることによって、その考えに同意してもらえることもあるし、異なる考えをもらえることもあります。経験も価値観も異なる人々と対話することによって、多様な考えが出てきて、自分の考え方や生き方が変わる可能性があります。
自分の言葉で語れば、自分の問題となる
大学・大学院では、主にジェンダー関係の科目を担当しています。ジェンダー学と言えば、社会学から始まった学問というイメージが強いのですが、哲学(特に現象学)の立場からジェンダーやマイノリティの問題を捉えることによって、この社会の中に存在するあらゆる関係性(男性/女性、正常/異常、異性愛者/同性愛者、シスジェンダー/トランスジェンダー、健常者/障害者、日本人/外国人、自己/他者など)について、じっくり考えられるようになります。
特に演習では、ジェンダーや時事問題に関係するテーマを設定し、哲学対話のようなことをしています。毎回テーマについて自分自身の経験に即して自分の言葉で語っていくことで、自分の問題として考えられるようになります。ジェンダーを哲学や対話の中で学ぶこととは、ある意味、想定外のことが起こる可能性を考えることなのかもしれません。
「当たり前」がいつ壊れるかは、わからない
現代社会の問題を自分のこととして考えることはとてもしんどいことですし、日常生活の中で何も問題がなければ、考えなくても生活できます。しかし、私たちは想定外の出来事に遭遇するケースがあります。例えば、人生の中で自分の性別に違和感を抱くとか、事故や災害に遭遇し、自分の「当たり前」を大きく壊されるケースも出てきます。
いつこのような想定外のケースが自分へ向かってくるかは、誰にもわかりません。だからこそ、人々と対話し、ともに考えることが必要になるのではないでしょうか。


あらゆる格差(ジェンダー、障害、経済、人種など)について深堀りすることによって、この社会がいかに不条理なのかを知ることができると思います。哲学の学びを通して、多くの格差について知り、それらを自分のこととして考えることは、社会の改善案を導くきっかけになります。
普段の私たちが持っている固定観念や慣習、感情やこだわりなどから、一旦距離を取り、関係性を俯瞰的・批判的に捉えることができます。哲学対話の実践を通して、SDGsに挙げられている問題について思考を重ねていきます。
◆先生が心がけていることは?
ものごとを問い考える場(哲学カフェなどの対話の機会)を提供することです。 SDGsという目標は個別に達成できる目標ではなく、17の目標と169のターゲットがネットワーク(蜘蛛の巣のイメージ)のように絡み合ってつながっているのです。一つの目標だけ達成すれば問題が解決するわけではありません。私自身は、哲学の立場からSDGsが向かっているベクトルそのものを批判的に問い直す必要もあると考えています。
「哲学プラクティスと当事者研究の融合:マイノリティ当事者のための対話と支援の考察」

池田喬
明治大学 文学部 心理社会学科 哲学専攻
【現象学を中心とする現代哲学・倫理学】 哲学的な知見を私たちの「生きづらさ」を改善するために使い、常にマイノリティ側に立って、物事を一緒に考えてくれます。
中澤瞳
日本大学 通信教育部 文理学部 哲学専攻
【メルロ=ポンティ、身体論、フェミニスト現象学】メルロ=ポンティの考え方を使って、女性の経験や身体性について深掘りし、また哲学を使って、ジェンダー問題を考えています。
梶谷真司
東京大学 教養学部 教養学科/総合文化研究科 超域文化科学専攻
【現実の多元性、身体と感情、近代化に関する研究】哲学対話の実践を通して、人々に「考える」楽しさや重要性を伝えており、またマイノリティとマジョリティを対話でつなげようとしています。
ジェンダーに関する思想(哲学)を基盤にして、「当たり前」や「普通」を再考する研究をしています。「男性と女性」、「健常者と障害者」、「自己と他者」、「精神と身体」、「正常と異常」などの関係性を考察し、共生社会の可能性を探っています。また、学生には『フェミニスト現象学入門 経験から「普通」を問い直す』(2020年、ナカニシヤ出版)を読むように勧めています。
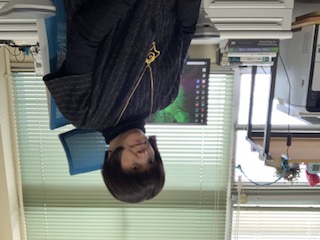
◆主な業種
(1)ホテル・宿泊・旅行・観光
(2)福祉・介護
(3)官庁、自治体、公的法人、国際機関等
◆主な職種
(1)システムエンジニア
(2)中学校・高校教員など
(3)福祉・介護関連業務・関連専門職
◆学んだことはどう生きる?
国家・地方公務員、コンサルタント、ホテルマン、中学校・高等学校の教員、雑誌の編集者、システムエンジニア、大手商社など多様な業界で活躍しています。私のゼミでは、学生の主体性を大切にしています。やりたいことがあれば、とにかく企画・運営してみるというスタンスで見守ります。ゼミ生の多くは、ジェンダーや哲学対話などを学んで、多様性を尊重して他者の語りを聞く力、自分の考えを伝える力などを活かした業務に就いています。
神戸大学国際人間科学部発達コミュニティ学科では、人間の発達の多様性について前向きに捉え、多様な人々と共生できる社会を実現するために必要な力を身につけた人を育てています。特に、人間の身体、心理、表現、行動などの発達プロセスを考え、人間の多様性や脆弱性と向き合えるように、様々な形のエンパワメントを考える学際的な研究をしています。多様な分野から専門家や研究者が集結して、新しい知を生み出しています。
 |
Q1.日本以外の国で暮らすとしたらどこ? オーストラリア。9年間住んで、楽しかったから。多文化共生社会だから。 |
 |
Q2.一番聴いている音楽アーティストは? Mr. Children。特に、『終わりなき旅』がお気に入りです。 |
 |
Q3.感動した映画は?印象に残っている映画は? 『マトリックス』、『攻殻機動隊』など。 基本的にSFが好きです。 |
 |
Q4.熱中したゲームは? スーパーマリオブラザーズ(あまり得意ではなかったですが...。) |
 |
Q5.大学時代のアルバイトでユニークだったものは? シドニーの日本人向け情報誌の編集作業とコラム担当、戦時中の歴史資料の英訳 |









