「作る」「買う」から「借りる」へ 着物の変容とその意味を問う

衣食住を超えて
衣服は衣食住のひとつであり、わたしたち人間が生きていくうえで欠かすことのできないものです。また衣服にはファッションという流行現象があったり、着物やチマチョゴリなどの伝統服あるいは民族服があったり、さらには服になる前の生地としての布など、様々な問題が複雑に交叉しています。なので、「なぜ人間は服を着るのか」、「どのようにして服をわたしたちは着ているのか」といった様々な問いが出てきます。
戦後から現在 着物との関係は大きく変化
こうしたいくつもの問いがあるなかで、現在取り組んでいるのは現代社会における着物の変容に関する研究です。主に戦後から現在に至るなかでわたしたちと着物の関係は大きく変わっていきました。それはたんに着物が生活着から非日常着へと変貌を遂げたにとどまりません。
そこには着物が「作るもの」あるいは「作り変えるもの」から「買うもの」へと、そして「借りるもの」になりつつあるという、わたしたちと衣服の関わり方そのものの変化がみられます。
着物には思い出も受け継がれていた
たとえば、着物を作ることは決して自分のためだけではなく、誰かのために、他者へと贈るためにも作られていました。また、着物を買うことはそれを持ちうることで、個人の箪笥やクローゼットを埋めそれぞれの物語になると同時に、祖母や母の記憶や思い出も受け継がれていました。
けれども現在、成人式の振袖や観光地でみかける着物などはその多くがレンタルによるものであり、着物を借りるという行為はそのどちらでもありません。では、そのときわたしたちは何のために着物を着ているのでしょうか。どうして衣服を着るのでしょうか。そうした具体的な対象とともに抽象的な思考をめぐらせています。
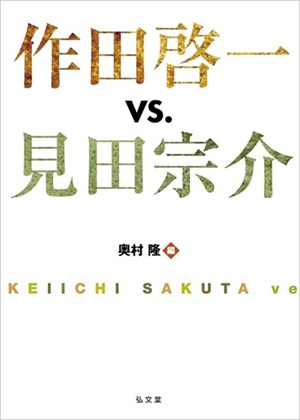
修士課程のときに社会学を専攻するなかで、より具体的な対象から考えてみたいと思いました。もともと文化や芸術に触れることが好きでしたが、そのなかで衣服あるいはファッションから始めることにしました。それは、衣服が根源的でかつ先鋭的な事象だと感じたからです。であると同時に、それについてわたしたちは容易に語りながら、いつもすり抜け常に掴み損ねてしまう、何か朧げな捉えどころのなさに興味を持ちました。
「戦後日本社会における和服の歴史社会学的研究」
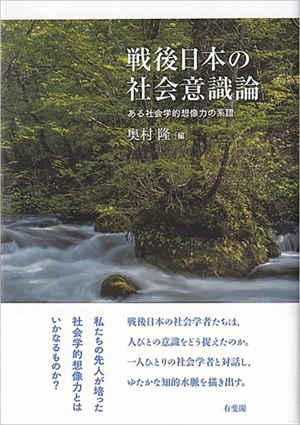
本学科が特徴的なのは他の学部や学科とは異なり、なにより衣服やファッションという対象を基に、文系・理系を問わず様々な学問分野の先生方がいることです。デザイン学や化学、経営学や教育学、社会学や心理学などの領域から、製作や実験、デザインやビジネス、カルチャーなど総合的に衣服やファッションに関わる点を学び、そのなかから各自専門分野を選ぶことが特徴であり、とても面白いと感じています。

| Q1.18才に戻ってもう一度大学に入るならば、学ぶ学問は? 哲学や美学など興味は尽きませんが、やっぱり社会学だと思います |
|
| Q2.日本以外の国で暮らすとしたらどこ? 綺麗な海がみえて、一年中暖かい国を探しています |
|
| Q3.一番聴いている音楽アーティストは? バッハとキース・ジャレット |
|
| Q4.大学時代のアルバイトでユニークだったものは? 長崎にて精霊流し終了後の清掃 |
|
| Q5.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? ピアノと散歩、甘いものを食べること |







