障害のある子どもの発達を支える地域の療育施設

地域での支援に大きな役割
私の研究テーマの1つは「小学校就学前の子どもの生活を豊かにする地域での支援のあり方」です。
日本では小学校就学前の子どもの生活を支える専門機関として、幼稚園や保育所、幼保連携型認定こども園などの幼児教育施設や、児童発達支援センターなどの療育施設・事業所が整備されています。
私が特に専門とする障害のある小学校就学前の子どもは、幼児教育施設で日々の生活を送りながら、障害に応じた支援を療育施設・事業所で受けているケースがあります。療育施設・事業所は、子どもの発達を支えるとともに、その保護者や幼児教育施設の保育者の保育実践を支える専門機関として、地域での支援に大きな役割を担っています。
現在は、この療育施設・事業所が、日本社会の中でどのように整備されてきたのかを解明しようと研究しています。
事業を立ち上げてきた歴史を後世に
療育施設・事業所は、誰かが行動を起こさなければ整備されてはいきません。日本の歴史の中では、行政や学校の教員、保護者などの民間の方々が行動し、事業を立ち上げてきました。この歴史を後世に伝えていくことが、今に生きる私たちの使命と考えています。
私自身も、中学校、高等学校段階からボランティア活動に参加する中で、障害のある子どもたちと出会い、「障害のある人とない人が具体的に接し関わりあう中で、全ての人の尊厳が守られる社会」である共生社会に関心をもちました。
ぜひ、みなさんも積極的に地域の中で行われている活動に参加して、新たな出会いをつむぐことで、興味関心を広げていってください。
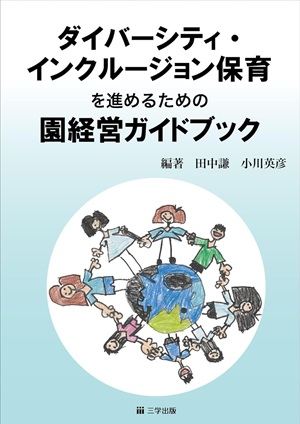
大学、大学院で、幼児教育・保育や障害児支援について教育学を中心に学ぶ中で、子どもの地域生活は教育だけでなく、社会福祉や政治、政策、経営等複数の領域から複層的にとらえる必要性を考えるようになりました。
そのような経緯から、現在の研究テーマは複数の学問領域の知見を応用して分析し、新たな知見を創出する「学際的研究」を志向しています。そのため、博士号も「教育学」「学術」と2つ取得しました。
「日本の療育制度の整備過程における地方行政および民間事業の役割と意義」
日本大学文理学部教育学科は、教員免許を取得可能な教職課程を有しており、多くの卒業生が学校現場で活躍しています。しかしながら、その特色としては、教員養成を中心とする学科ではなく、教育という営みを特に思想、哲学、歴史を中心に、科学的に探究することに軸足を置いた教育学を修める学科です。
その中で私は教育と福祉にまたがるテーマを中心に、複層的なアプローチを試みる「教育と福祉」等の科目を担当しており、私のゼミでは教育、福祉を横断した学問の面白さを追求できることが強みといえます。

総合的な探求(学習)の時間などで、地域にどのような障害のある小学校就学前の子どもを支援する機関が存在して、機能しているのかを、ぜひ調べてみましょう。
幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園や、「〇〇支援センター」など、地域の中でどのように分布して整備されているのかマップを作成したり、どのくらいの子どもたちが支援を受けているのか、都道府県や市区町村の事業報告書やWebサイトの内容を分析したりしてみましょう。
みんなの学校
映画配給:東風
すべての子どもたちに居場所のある学校づくりをめざしたドキュメンタリー映画で、自分も他者も大切にする生活がどのように実現できるのかを考える上で参考になります。
[webサイトへ]
| Q1.18才に戻ってもう一度大学に入るならば、学ぶ学問は? 政治経済学部などで政治学や政策科学を一から学び直したいです。 |
|
| Q2.一番聴いている音楽アーティストは? Mrs. GREEN APPLEさんの「点描の唄」が好きです。 |
|
| Q3.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? YouTuber「東海オンエア」さんのファンなので、愛知県岡崎市を観光するのが趣味です。 |
|
| Q4.好きな言葉は? 笑われてもいいから「夢」を叫び続けたい。(YouTuber東海オンエアより) |





