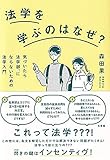人が人を罰するということ 自由と責任の哲学入門
山口尚(ちくま新書)
私たち人間は自らの行為を自由に選択できているのか、つまり自由意志を持っているのかという問題について、自由意志を持っていないと答える自由意志否定論という立場がある。私たちが自由でないとすれば、私たちが互いを責めたり罰すること、そして非難としての刑罰に意味はないのではないか? そうはいっても、私たちは互いに非難することをやめることができるのだろうか?
本書はそのような観点から、刑罰の意味を検討し、自由意志否定論を批判しつつ、「人間として生きること」を問うものである。刑罰、自由意志、非難としての責任といったものをめぐる議論の一端を知ってもらうためにおすすめの本です。
「責任なければ刑罰なし」の責任主義の意味を問う

刑罰とは、犯罪者を非難するもの
刑罰って何だろう? なぜ犯罪者には刑罰が科されるのだろう? 私たち刑法学者は普通、刑罰とは、犯罪を行ったことに関して犯罪者を非難するものだと考えている。つまり、刑罰を科すことによって、犯罪という悪いことをした人を責めているのである。
だから、悪いことをしたが、非難することができない人に刑罰を科すことはできない。刑法は、非難できる(非難可能性がある)ということを「責任がある」といい、「責任なければ刑罰なし」という責任主義を採用しているのである。
私たちは自由に行為をしているのか
では、悪いことをした人が「そうせざるを得なかった場合」(他の行為を選べなかった場合)や、洗脳されるなどして操られて悪いことをしてしまった場合に、皆さんはその人を非難するだろうか? おそらくしないだろう。このように自由に行為を選べなかった人には非難可能性はないのである。
ここで、私たちの世界で起きる全ての物事が、私たちがどのような行為をするかも含めて、過去と自然法則によって決定されているとすればどうであろうか? 私たちは自由といえるだろうか? 自由でないとしたら、どのような行為をしても私たちは非難され得ないのではないだろうか?
AIやロボットを非難できるか
このようなことを考えていると言ったら、犯罪者が非難されないのはおかしいと思うかもしれない。しかし、その犯罪者も生育環境や貧困といった生活状況ゆえに、犯罪をせざるを得ない状況に追い込まれていたのかもしれない。しかし、犯罪に至ったことを犯罪者の責任にして、それらの原因に目を向けないことは、本当に犯罪対策として正しいのだろうか? 上の問いは、そのようなことを考えるきっかけともなるのである。
さらに、上の問いは、人間が設計したプログラムとデータに基づきながらも自律的に動くAIやロボットが刑事責任を負うのかという問題にもつながっている。AIやロボットは非難できるのだろうか?
これらの最新の問題にまでつながるのが、「責任」とは何かという問いであり、責任主義の意味を問い直す研究なのである。
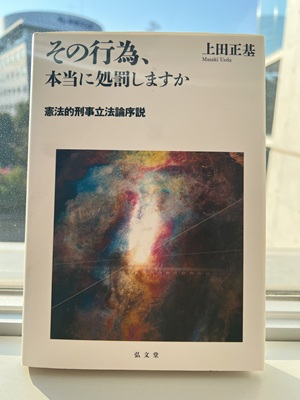
私は、法科大学院(ロースクール)を経て司法試験に合格した後に、本格的に研究の道に進みました。ですから、刑法だけを研究してきた時間は少ないかもしれません。けれども、司法試験の勉強をするなかで、刑法以外の様々な法分野に触れました。そのことが今の研究に至るきっかけともなっています。
研究の道に進んだ最初の頃に、ドイツ連邦憲法裁判所が兄弟姉妹間の性交処罰規定を合憲と判断した事件を紹介する雑誌記事に触れました。そこから、憲法と刑法の関係、とりわけある行為を処罰する刑法の条文が違憲とされるのはどのような場合かを研究するようになりました。これが、刑罰という制度でどこまでできるのかを考えるという、今まで続く研究テーマにつながっています。
「刑事立法の限界としての責任主義の再検討」
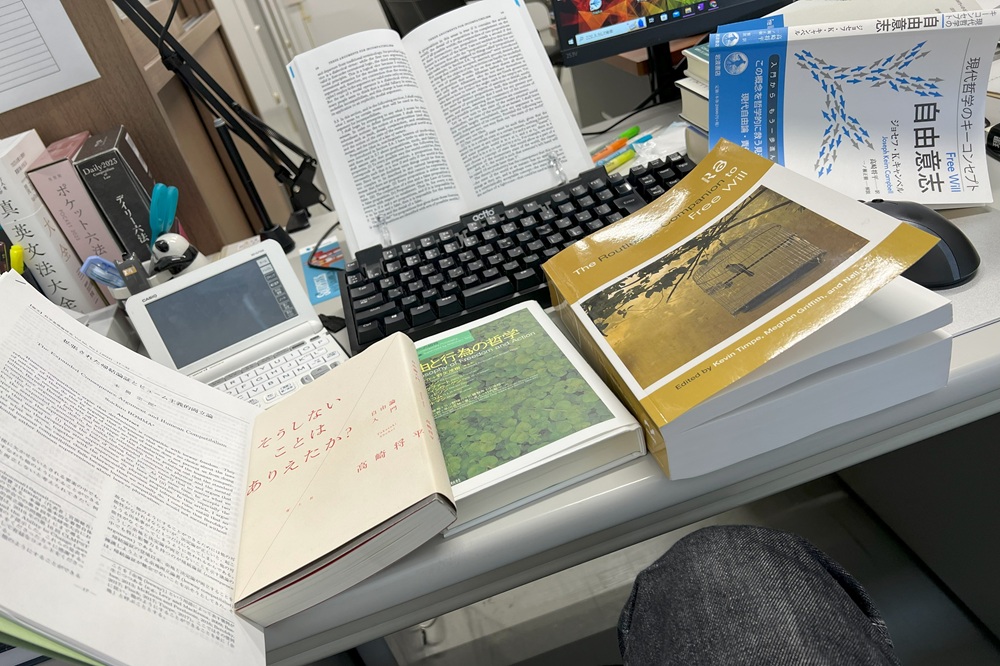
◆主な業種
(1) 官庁、自治体、公的法人、国際機関等
(2) 小売(百貨店、スーパー、コンビニ、小売店等)
(3) 通信
◆主な職種
(1) 保安(警察・消防・警備等)等
(2) 営業、営業企画、事業統括
(3) 一般・営業事務
◆学んだことはどう生きる?
私のゼミは、刑法を扱うゼミなので、卒業後、警察官になる人も比較的に多くいます。警察官になった卒業生が、ゼミに来て警察官の業務ややりがい等を説明してくれることもあります。卒業生の一人は、ゼミで学んだ刑法の知識が、警察学校や警察官になった後にも役立っていると話してくれたことがあります。
神奈川大学法学部では、大学の授業(座学講義)で習得した知識をつかって実践の場面で「答えを出すこと」を目標にPBL(Project Based Learning 問題解決型学修)を導入しています。
例えば、(1)国際的な問題を英語の資料や映像を使いながら学んだり、グローバルに活躍するゲストスピーカーからお話を直接うかがってディスカッションをしたりする少人数科目であるGlobal Perspective Program (GPP)特修、(2)警察OBの方が運営し、警察官が事件・事故等の実務で何をしなければならないのか、具体的な事例をもとに考えていく警察官実務特修、(3)神奈川県内の自治体の現役職員より、地域の特性に応じた多種多様な施策についてお話しをいただき、かつ、日々直面している課題や問題点を提示していただいて、提示された課題等について自ら考え、学んだことを実践していく自治体実務特修があります。
AIによる自動運転車が事故を起こし、歩行者を死亡させてしまったという場合、誰にどのような理由で責任を負わせて刑罰を科すべきなのか、その人に刑罰を科した場合に(その人や社会全体に)どのような不都合が起こり得るかを考えてみましょう。
責任を負う可能性がある人としては、(1)運転者(運転席に座っている人)、(2)事故を起こした自動車を製造した人、(3)自動運転車に搭載されたAIを開発した人等が考えられます。
法学を学ぶのはなぜ? 気づいたら法学部、にならないための法学入門
森田果(有斐閣)
「法」とは、特定の意思決定や行動を促したり、抑止したりするインセンティブ(誘因。簡単に言えば「アメとムチ」)を設定するものだという観点で、「法学を学ぶのはなぜ?」を教えてくれる入門書。文系学部で何学部に入るのか悩んでいたり、法学部に入って何かいいことがあるんだろうかと思っていたりしている人は是非読んでほしい。
とはいえ、最初に書いたように「法」を理解する考え方は、法学研究者の中で必ずしも共有されているわけではない。特に、刑法ではそうかもしれない(かもしれないと書いたのは、私自身は本書の筆者と同じような考えだからである)。とすれば、法学部に入って、その大学の先生の授業を聞いたら「法」に対する全く違う考えに触れることができるかもしれない。そのような面白さも本書にはある。
尊属殺人罪が消えた日
谷口優子(筑摩書房)
なかなか手に取ることが難しくなっている本でもあるし、この本を読んでほしいというわけではない。だからここで本書を挙げるのは間違っているかもしれない。しかし、裁判官や弁護士といった法律家を目指している人には必ず知ってほしいのが、本書で書かれている「尊属殺重罰規定違憲判決」をめぐる実話である。
判決自体は、NHK朝の連続テレビ小説「虎に翼」でも出てきたので知っている人もいるかもしれない。また、判決の結果やそれが持つ法的意味は法学部に入学すれば必ず学ぶ。けれど知ってほしいのはそれではない。判決の対象となった事件がどのような事件であったのか、被告人の弁護人はどのようにして弁護を引き受け、どのような思いで弁護をしたのかを含めて知ってほしいのである。そうして、犯罪を行ったにもかかわらず非難すべきでないように感じられるのはどのような場合なのか、そして法がいかにしてそのような人を救うのか(あるいは、苦しめるのか)といったことを考えてほしい。
| Q1.感動した/印象に残っている映画は? 新海誠作品 |
|
| Q2.学生時代に/最近、熱中したゲームは? ファイナルファンタジーシリーズ・グランツーリスモシリーズ |
|
| Q3.大学時代の部活・サークルは? 憲法研究会(憲法を研究しているわけではなく、集まって法律の勉強会等をやっていたサークル) |
|
| Q4.研究以外で、今一番楽しいこと、興味を持ってしていることは? 子育て |
|
| Q5.好きな言葉は? 明日の自分は今日の自分より成長している。今日できなかったことも、明日はできるかもしれない。だから、「いつ死んでも後悔する生き方」をする。 |