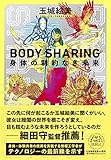◆先生の研究分野である「ヒューマン・コンピュータ・インタラクション」とはどのような研究なのでしょうか。

HCI (ヒューマン・コンピュータ・インタラクション)とは、人間とコンピュータの関係や、お互いに何らかの作用をすることに関する研究領域です。「インタラクション(Interaction)」とは「相互作用」という意味です。
身近なものでわかりやすいものでいうとスマートフォンにある画面タッチ機能です。画面タッチ機能でヒトが情報を入力することで、ヒトからコンピュータであるスマートフォンにスムーズに情報交換を行っているのです。この画面タッチ機能は、昔のHCIの研究成果です。画面タッチ機能は、工学的な設計だけではなく、ヒトの手の形状、ヒトが画面タッチ機能を使ったときにどのように感じるのかなど、いろいろな観点から研究されてきました。HCIは、工学的なこと以外にも、言語学、心理学、社会学など幅広い分野にまたがった学際領域となります。
◆先生の研究は、どのような成果につながるのでしょうか。
私は、触感の共有の研究から、身体の共有の研究を行っています。ヒトの身体の体験を世界中の人々と共有できることを目指しています。将来的には、1人のヒトの人生経験だけはなく、いろいろなヒトの人生経験を世界中で共有できる成果になると考えています。
◆研究テーマをどのように見つけたのかを教えてください。
「身体の共有」の研究は、高校時代に長期入院していた際に、家族旅行に行けなかったことが悔しかったのがきっかけです。もしも病院にいながらにして外に出て、皆と同じ体験ができればどんなにいいかと思い、自ら研究を始めました。
◆この分野に関心を持った高校生にアドバイスをお願いします。
HCIは様々な分野にまたがるため、とても興味深い分野です。まずは自分が実現したいことや、叶えてみたいことを考えてみて、それをテクノロジーによってどう実現できるだろうか、と想像してみてください。そういったところから始めてみるといいと思います。
こちらの玉城先生の記事もどうぞ
◇WIRED記事:「触れるVR」が、現実を変える
◇TEDxUTokyo2012 「手、創造」
PSVR(プレイステーションVR)(ソニー株式会社)、GearVR(SamSung)
視覚に関するHCI分野の研究成果が社会実装されたものです。
誰のためのデザイン?―認知科学者のデザイン原論
D.A.ノーマン 岡本明、安村通晃、伊賀聡一郎、野島久雄:訳(新曜社)
著者のノーマンは認知学者で、HCIにも関わる分野の方です。日常、私たちが目にするもののデザインが、どのように私たちに認知されて、良い悪いといった評価になるのかを、心理学、認知学(何かに対して脳が知覚する性質を研究する分野)の分野で説明しています。
本書からは、私たちの日常身の回りにあるもののデザイン(工夫)に気づかされます。何もかもが合理的で短時間で解決することが、必ずしも便利であるとは言えません。ヒトに最適な仕組みを考えて設計されている物があるという点を読んでほしいです。
日常的に利用しているものは、どのように考えられてそこにあるのか、どのようにして私たちに使われているのかを見つめ直し、改めて自分の周りがどのように作られているか、どのように社会が作られているかを考えるきっかけになると思います。
新しいヒューマンコンピュータインタラクションの教科書 基礎から実践まで
玉城絵美(講談社)
HCIの概要から、人間やコンピュータの情報の入出力に関する特性、インターフェースを設計する際の考え方や評価方法、そして近年注目されている技術までを、図や具体例を交えてわかりやすく紹介しています。この分野は、「新しいものをつくる人」だけのためのものではありません。今ある仕組みをどう改善していくか、という視点にも大いに役立ちます。身の回りの社会やテクノロジーの“しくみ”に目を向けてみたい高校生に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。
BODY SHARING 身体の制約なき未来 (未来のわたしにタネをまこう 3)
玉城絵美(大和書房)
この本では、ひとりの体験が他の誰かの体験になる――そんな未来のあり方を示しています。メタバースに「身体性」を取り入れることで、単なる映像や通信を超えて、人と人とが“感覚ごと”つながる社会を目指す内容です。テクノロジーの最前線とその先にある未来の姿が描かれており、これからの社会や生き方に興味がある方に読んでほしい一冊です。
感覚まるごとシェアできる、体験のデジタルマーケット「Maaart」
(H2L株式会社)
BodySharing技術を活用し、身体の感覚をデジタルデータとして販売、提供するオンラインマーケットです。
[webサイトへ]
感覚共有できるメタバースオフィス「BodySharing® for Business」
(H2L株式会社、株式会社乃村工藝社)
BodySharing技術を活用し、ユーザの状態を「元気度」と「リラックス度」としてアバターにリアルタイムに反映することで、コミュニケーションを生まれやすくするメタバース空間です。
[webサイトへ]